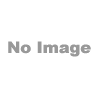ROCK IN JAPAN FES.2022 day2 @蘇我スポーツ公園 8/7
- 2022/08/11
- 00:13
2日目。前日は帰りの混雑によって帰るのがかなり遅くなったために疲労が蓄積しているが、その感覚を持ったまま次の日に臨むというのもロッキンの2日目ってこんな感じだったなっていうことを思い出させてくれる。
10:30〜 ハルカミライ [GRASS STAGE]
10時くらいに、まだまだ始まるまで時間があるし、暑くなってきたから冷たいものでも食べるかと思って夏フェスおなじみのスイーツであるいちごけずりを呑気に食べていたら、すぐ裏のGRASS STAGEからは早くもサウンドチェックと称したメンバーによる本気の演奏が始まったので慌てて食べてからステージへ。先日に地元の八王子のホールで2daysライブを終えたばかりのハルカミライがついにGRASS STAGEというロッキンのメインステージのトップバッターである。
このGRASS STAGEではロッキンオン社長の渋谷陽一の朝礼がある。そこで渋谷陽一は前日に駅に機動隊が出動してもしもの際に備えていたというが、そんな必要が全くなかったくらいに参加者のマナーとモラルが良かったことを褒めていたのだが、そんなルールをちゃんと守る若者としてこのハルカミライを紹介する。
「ずっとこのバンドが好きで、うちのフェスに入れろって言ってきたから、ロッキンオン内では社長のバンドって言われてる(笑)」
というのはハルカミライのファンとしても、渋谷陽一のファンとしても実に嬉しいことであるが、確かにハルカミライはまだここまでの存在になる前のCDJ18/19からロッキンオンのフェスに出ていた。それも社長のゴリ押しだったということだろうか。
そうした紹介(まさか渋谷陽一の紹介でハルカミライが登場するライブを見れるなんて全く思ってなかった)から、おなじみの新世界リチウムの「喝さい」が流れて小松謙太(ドラム)、関大地(ギター)、須藤俊(ベース)の3人が先にステージに登場し、最後におなじみのフラッグを持った橋本学(ボーカル)が登場すると、
「今日、20曲やるから(笑)」
と口にしてから「君にしか」「カントリーロード」の鉄壁の流れのオープニングとなり、関はアンプの上に立ってから大ジャンプを決める。その光景を映した写真があったならすぐさま公開してほしいくらいに鮮やかな姿だったのだが、間奏でのブレイクで橋本は
「昨日、ワンピースの映画見てきた!」
と発表すると須藤も
「今からネタバレしまーす。聞きたくないやつは耳を塞げー。ルフィとナミが結婚しまーす」
と嘘でしかないようなことを口にすることによってネタバレを回避してみせる。その全てが実に楽しそうというか、それは野外の開放感によってもたらされているものもあるのかもしれない。
すでにリハでも2回演奏されていたことによってこの日3回目の「ファイト!!」から一気にパンクに振り切れていくスイッチが入ると、「俺達が呼んでいる」では須藤と関が広いステージをスライディングしたり、橋本はステージ左右に伸びる通路の柵に跨って歌ったりとやりたい放題であるが、それでも決してルールを破ることはないというのはさすがであるし、それはハルカミライにとってはキチンとルールを守ることが出来る人ほどカッコいいという価値観によるものだろう。
だからこそ橋本は
「ここが世界の真ん中!」
と高らかに宣言した「春のテーマ」の曲中に客席の一部を指差して、
「兄ちゃん、あんたはライブを楽しむプロだ。だから撮影するのは撮影のプロのカメラマンの人に任せてくれ」
と言った。前方エリア(しかも多分かなり最前に近い位置)で堂々とライブを撮影するのもそれはそれで凄い気もするが、その人を決して悪者にするように叱ったりはしないというあたりが本当にハルカミライのメンバーの人間性が出ているし、それを鳴らしている音からも感じられるからハルカミライの音楽やライブが好きなのだ。自分もこういう人間になることができたらな、とメンバーよりも年上でも思ってしまう。
目標を20曲に設定していることによって中盤でも容赦なくショートチューンを連発するのであるが、
「夏の曲をやります!」
と言って演奏された「夏のまほろ」での晴れているのに(橋本は「太陽呼んじゃった!」と狙って奇跡を起こしたように口にしていたが、それもこのバンドのライブを見ると本当にそう思える)微かに雨が顔に当たっているというシチュエーションのあまりの見事さ。35°Cに届きそうとまではいかないけれど、このバンドのライブが我々をそれくらいに暑くしてくれる。
さらには橋本のボーカルの伸びやかさが青い空に突き刺さっていくかのような「ウルトラマリン」では
「1番綺麗な君を見てた」
のフレーズに合わせて観客が一本指を突き上げるのだが、まさにこの光景こそが1番綺麗なものであるかのようだ。
さらにメンバーが入り乱れまくりながらコーラスをしまくる「PEAK'D YELLOW」ももはや完全にフェスにおけるアンセムと呼べる存在になっているが、曲終わりでは小松が前に駆け出してきて橋本が「世界を終わらせて」を歌う隣で全員が並んで体を揺らす。そうしてから戻って楽器を鳴らすことによってより込み上げてくるものが確かにある。なんだかみんなで肩を組んでこの曲を歌いたくなるような。それは時折メンバーがやることでもあるのだけれど。
そして橋本は
「眠れない夜を超えて ROCK IN JAPANに来たんだ」
と「アストロビスタ」を歌い始めると、曲中の最も極まる部分と言える
「忘れないでほしい」
のフレーズをを少し飛ばしてまでも、
「ROCK IN JAPAN、会いたかったぜー!」
と高らかに思いっきり叫ぶ。ああ、本当にそうだ。2019年の1回しか出演したことがないし、このフェスでおなじみと言える存在ではない。でもどのフェスよりも自分が大好きでずっと通ってきたこのフェスで会いたかった。こんなに大きなフェスの大きなステージでハルカミライのパンクが響く瞬間を目にしたかったんだ。それはこの日ついに現実になった。日本最大級のフェスのメインステージで、ハルカミライの音楽が確かに鳴っていた。メンバーもこのフェスを好きでいてくれていたらそんなに嬉しいことはないけれど、こんなライブができる場所なら絶対に好きに決まっている。
しかし体感的にもあまりにあっという間だったこともあり、須藤が時間を確認するとまだかなり時間があるということで、JAPAN JAMの時と同じようにここからは時間の許す限りに怒涛のショートチューンの連打となるのだが、その口火を切る「Tough to be a Hugh」を演奏しようとすると橋本はバンドを制して
「俺の歌から始める」
と言ってアカペラから歌い始めたあたり、本当に何にも決めていない、その場でその瞬間に全て決めているんだろうなということがわかる。それは毎日のようにライブをやっているバンドだからこそできる野生のカンのようなものだろう。
そうしてショートチューンを連発しまくって時間ピッタリになったかと思いきや須藤は
「でも前説2分押したからもう1曲やります!」
と言って、リハも含めたらこの日6回目となる「ファイト!!」で全てを出し尽くした。もう何回あいつはぶっ飛ばされたんだろうかと思うくらいに。
リハも含めたら余裕で20曲を超えていた。こんなライブは間違いなくハルカミライにしかできない。それはロッキンという場所であってもハルカミライが変わることはないということであるし、きっとこれから毎年このステージでこんなライブを見ることができる。ハルカミライのファンはもうハルカミライを見るためにこのフェスのチケットを取っても絶対後悔しないというか、そうすべきだなと思うくらいにこの日1発目にしてあまりにも凄まじくハルカミライらしいライブだった。
リハ.ファイト!!
リハ.エース
リハ.フュージョン
リハ.Tough to be a Hugh
リハ.To Bring BACK MEMORIES
リハ.ラブソング
リハ.ファイト!!
1.君にしか
2.カントリーロード
3.ファイト!!
4.俺達が呼んでいる
5.春のテーマ
6.ファイト!!
7.フュージョン
8.夏のまほろ
9.ウルトラマリン
10.PEAK'D YELLOW
11.世界を終わらせて
12.アストロビスタ
13.Tough to be a Hugh
14.フュージョン
15.ファイト!!
16.To Bring BACK MEMORIES
17.フルアイビール
18.ファイト!!
11:25〜 オレンジスパイニクラブ [HILLSIDE STAGE]
もともとはこの枠はなきごとが出演する予定だったのだが、メンバーのコロナ感染でキャンセルになったことによって、このオレンジスパイニクラブが急遽出演することになった。何なら代打じゃなくて普通に出演していても全くおかしくない存在だと自分は思っているバンドである。
メンバーがステージに登場すると、実に普通というか見た目の派手さは一切ないバンドなのであるが、ベースのゆっきーはどこか髪が長い時の菅田将暉のように見えるのが不思議であるし、ドラムのやはり髪が長いゆりとが黒のサングラスをかけているというのも少し意外である。
するといきなりの、SNSでバズってこのバンドの存在を知らしめた「キンモクセイ」という最大の代表曲を1曲目に演奏することによって歌詞のとおりに「あんた最高」と思わせてくれるのであるが、もしかしたら共感できるラブソング的に広がったかもしれない曲であるのだが、兄であるスズキユウスケのボーカルも、弟であり時にはツインボーカル的なパートも担うスズキナオト(ギター)のコーラスも声に甘さは全く感じられない。むしろその声はロックバンドをやるためにもたらされたかのような強い攻撃性を感じさせる。
だからこそその「キンモクセイ」のイメージをライブという場で覆すかのようにーというよりはかつては銀杏BOYZに影響を受けてドーテーズという名前で活動していたという個人的にラブソングよりもはるかに共感しまくりのエピソードを持つバンドであるだけにそうした面こそが本質であるかのように、「君のいる方へ」「スリーカウント」とスズキ兄弟の荒々しさすら感じる歌声ともはやパンク的と言えるようなバンドサウンドをぶっ放すように演奏していく。これは「キンモクセイ」が聴きたくて観にきたというような人でもイメージが変わらざるを得ないだろう。
しかしながらユウスケは本来このステージに立つはずだったなきごとへ拍手を送ったりするあたりからはダメ人間ではあれどクソ野郎ではないというこのスズキ兄弟をはじめとしたこのバンドのメンバーの人間性を感じさせてくれる。しきりに2日前に急遽出演が決まったということも口にしていたけれど。
リズミカルに体を揺らすような「タルパ」から、もうこの歌詞はこのくらいに振り切ったダメ人間でないと書くことはできないであろう、「キンモクセイ」のイメージだけで来た人は引いてしまうかもしれないくらいにどぎつい歌詞が並ぶ「モザイク」、さらには破壊的というか自己破滅的とすら言えるくらいのパンクサウンドの「急ショック死寸前」と、むしろこのバンドの本質の部分を見てくれと言っているかのようですらある。だからこそユウスケは
「ロッキンは憧れの一つ。急に出ることになったから実感があんまりないけど。
でも俺たちもツアーを廻ります。今日見て、なんか思ったよりも良いなとか、こんなバンドなんだって思ってくれたりしたあなたに来てほしいです」
と言ったのだろう。この曲たちをしっかり受け止めてくれるような人がたくさんいることをわかっているのだ。
そして最後に演奏されたのは、タイトル通りに銀杏BOYZの影響をモロに感じるような「敏感少女」。その演奏する姿を見ていて、自分の中でこのバンドのイメージがハッキリと変わった。「TikTokでバズって〜」みたいな形容詞は自分には縁遠く感じてしまうけれど、むしろこのバンドは自分のように銀杏BOYZに影響を受けてしまって、自分には音楽しかないと思ってしまうような奴のための音楽なんじゃないかと思った。だからユウスケの言葉の通りにツアーにも行きたいと思ったし、もし行ったらより一層自分のためのバンドだと思える気がする。
「また来年」
と最後にユウスケはボソッと口にしたけれど、その言葉が現実になって欲しいというか、なるべきバンドだと思った。まさかこんなにもカッコいいバンドだなんて。本当に「あんた最高」だった。
1.キンモクセイ
2.君のいる方へ
3.スリーカウント
4.タルパ
5.モザイク
6.急ショック死寸前
7.敏感少女
12:00〜 Hump Back [GRASS STAGE]
サウンドチェックからそのままステージに残って本番を迎えると林萌々子(ボーカル&ギター)は
「先に水飲んでおきや。これからライブ始まったらすぐに暑くなるから!」
と宣言する。JAPAN JAMでも2年連続で最高にカッコいい姿を見せてくれたこのステージにHump Backが帰ってきた。すでに日本武道館でもワンマンをソールドアウトさせているが、ついにロッキンでもメインステージへの登場である。
そんなこのバンドのストレートなロックサウンドを真っ直ぐに響かせる「LILLY」からスタートすると、やはり林のボーカルは空高くに突き抜けていき、ぴか(ベース)は本当にこのステージに立っていることが楽しくて仕方がないというように飛び跳ねまくりながら演奏しているのだが、いつもスウェットを着ていて暑くないのだろうか。顔にはやはり汗が滲んでいるが、それは白のロンTという出で立ちが変わらない美咲(ドラム)もそうである。
拳を振り上げるというよりも観客の体を心地良く揺らせてくれるようなサウンドの「恋をしよう」という曲をこの序盤で演奏するというあたりには大きなステージでのライブに慣れてきた余裕のようなものを感じさせるのであるが、林はここにいる全ての人=少年少女への想いを口にしながらも、
「1つだけロッキンに文句言っていい?HY見たかったー!」
と、自分たちのライブと被ってしまって見ることが出来なくなってしまったHYが青春のサウンドトラックの一つであることを口にする。JAPAN JAMでもモーニング娘。のライブを見て振り付けを踊っていただけに、硬派なロックンローラーというイメージもある林は実はかなり幅広い音楽の趣向を持っているようであるし、そうした音楽遍歴がこのバンドのメロディのキャッチーさに繋がっているんだろうなということが様々なスタイルや世代のアーティストが居並ぶフェスに出るのを見るとよくわかる。
すると林のボーカルとバンドのサウンドがさらに伸びやかに突き抜けていくことによって客席の少年少女たちも笑顔で拳を振り上げる「オレンジ」から、先程このステージに出演していたハルカミライにも通じるようなショートチューンの「宣誓」では林が自身のマイクスタンドをぶっ倒しながら歌い、その際にコードが絡まりまくってしまう。そのコードを直すスタッフを称えるというのもなんだか林らしい感じがする。
その林は前日に近くのホテルに泊まって前乗りしていたということを明かすと、
「ホテルの近くで夏祭りをやっていて、盆踊りが始まるっていうからベンチに座って待ってたら、隣に85歳のおばあちゃんが座ってきたから話してたら、今でも好きな演歌歌手のコンサートを見るのを楽しみに生きてるって言ってて。
それって私たちと一緒やん!って。何歳になっても好きなものがあるから生きていけるんやなって。だから私たちも明日ライブやってくるよって言って」
というおばあさんとのエピソードを話す。その話を聞いていて、自分は85歳になってもライブに行くことができているだろうかと思った。今のままならきっとそうなっているだろうけれど、その歳になっても音楽やライブが生きている理由になってくれていたら幸せだろうなと思う。好きなバンドがまだ活動してるっていうことでもあるのだから。
そんなMCから繋がるのは、そのおばあちゃんも含めて全ての少年少女への想いを込めて鳴らされた新曲「がらくた讃歌」。もうリリースが迫ってきているけれど、きっとこれからもこのバンドのライブを担っていくことになるであろうストレートなロックンロールである。
それは今に至るまでのこのバンドのライブ定番曲であり、「ティーンエイジ」というタイトルでありながらもここにいる全ての人に向けて歌われた「ティーンエイジサンセット」へと繋がっていく。それは歌い方や描き方は多岐に渡れど、このバンドが歌っていることはずっと変わらずにいるんじゃないかと思えてくる。
すでにMCをしたからか、普段は演奏前に林がギターを爪弾きながら思いを口にして演奏されることも多い「番狂わせ」は、ここまでに少年少女のための曲を歌ってきたからこそ、すでに大人になった自分のような年齢の人間が聴いても
「おもろい大人になりたいわ」「しょうもない大人になりたいわ」
と思うのであるし、それはメンバーもきっと同じ思いでこの曲を鳴らしているんじゃないかと思う。
だからこそこのフェスでのライブでも林のボーカルを軸にしたバラード曲「きれいなもの」の純真さがダイレクトに響いてくるし、こうした聴き入るようなタイプの曲を堂々と演奏できるのもまたこのバンドの強さであるが、その純真さはそのまま「拝啓、少年よ」へと繋がっていき、林が声を張り上げて
「空がキレイだぜ」
と歌う時に観客が腕を突き上げた真上に広がる空は雲がかかっていてもキレイに見えるというか、うっすら晴れ間が射していたのはこのバンドが招いたものなのだろうか。
そして
「みんなこの曲知らんだろうけど、知らんくても楽しめる曲やから!」
と言って演奏された、パンク的なサウンドの新曲の「僕らの時代」では時間がないのを察知したのか林が2人を
「急いで急いで!」
と急かして演奏したことによって、より曲のテンポが速くなってパンクさが強くなる。その時間との戦いもまた盟友であるハルカミライと通じるようなところがあるのだが、無事に最後まで演奏しきると安堵の表情を浮かべてステージから去っていった。その姿からはもはや貫禄にも似た頼もしさを感じるようになっていた。
林はよく歌詞を変えて歌ったり、曲中に思いを込めた言葉を口にしたりするが、ライブ後半には
「今年の夏はロッキンがあるから大丈夫!」
と口にしていた。それと同時にライブハウスでは毎日のようにこうしたライブが行われていることも。そうしてライブをすることによって守っていくという戦い方を選んだHump Backだからこそ、JAPAN JAMの2年を経てようやく夏にロッキンに出演することができた意味の大きさをわかっているはずだ。でもそれはこのステージが終着点ではなくて、これから先もずっと続いていく。そんなこのバンドがいてくれればずっと少年少女のままでいることができると思える。かつて初めてこのロッキンに来た時を思い出すかのように。
1.LILLY
2.恋をしよう
3.オレンジ
4.宣誓
5.がらくた讃歌
6.ティーンエイジサンセット
7.番狂わせ
8.きれいなもの
9.拝啓、少年よ
10.僕らの時代
12:45〜 フレデリック [LOTUS STAGE]
3年前にはひたちなかのGRASS STAGEにも立った、フレデリック。JAPAN JAMでもCOUNTDOWN JAPANでも「俺たちの」という形容詞を付けていただけに、3年振りとなるこのロッキンのステージにも並々ならぬ思いがあるはずである。
「ジャンキー」のリミックスのようなSEでメンバーがステージに現れると、髪に緑色が混ざっている割合が増えてきているように見える三原健司(ボーカル&ギター)が
「ロッキン、3年振りの開催おめでとうございます。3年振りのロッキンのフレデリック、40分1本勝負、よろしくお願いします!」
と自らに気合いを注入するかのように口にしてからいきなりの「KITAKU BEATS」で軽快かつコミカルな電子音的なサウンドを赤頭隆児(ギター)が奏で、三原康司(ベース)の音階的にも肉体的にもうねりまくるベースと高橋武のアタック感の強いドラムのリズムに合わせて観客は手拍子をして踊りまくる。
すると健司は早くもハンドマイクになって、歌詞に合わせて客席に手を振りながら
「よく来たね〜」
と声を掛けるのは「シンセンス」であるが、サビで思いっきり手数を増やすだけではなくて、高橋のドラムは間奏で激しいビートのアレンジを施しており、それがそのままこのライブならではのものとして響くと、それはやはり気合いに満ち溢れているからこそのものであることが伝わってくる。
それは歌詞の通りにみんな優勝するためのダンスアンセムである「オンリーワンダー」でもやはりビートの強さがそのままより踊れるサウンドとなって我々を踊らせてくれるのであるが、そんな中で演奏されたこの時期にピッタリ過ぎるくらいにピッタリな「熱帯夜」では健司が左右に手を振る姿に合わせて観客も同じように手を振る。
ライブ初披露だったJAPAN JAMではその手を振るタイミングがなかなか合わずに健司も苦笑いしていたのであるが、それからツアーの各地や代々木体育館というアリーナでも鳴らされたことによってこの曲はやはり大きく化けた曲になったし、健司は高音部分がキツそうに感じる時もあったが、ハンドマイクゆえにカメラに目線を合わせるというか、ステージ上でヤンキー座りのようにしてカメラを見つめて歌ったりと、ロックスターっぷりがまたも大きく向上している。だからこそこうして巨大なステージで見るのがしっくりくるというか。
そうしてここまでは今の最新のフレデリックを見せつけるような内容になっていたが、ここで健司はロッキンには2015年からずっと出演し続けていることの感謝を告げると、その初出演時に演奏していた「愛の迷惑」を実に久しぶりに演奏する。きっとファンはみんな聴きたい曲であるということをわかっているからこそ、こうしてここで演奏されることによってロッキンへの思いの強さを知ることができるし、まだ規模が拡大する前だったとはいえ、PARK STAGEを初出演にして満員にしてみせたあの時のライブはこのバンドがいずれメインステージに立つということを予期しているかのようであった。もちろん今鳴らされるこの曲はその強靭なビートと健司のボーカルとフロントマンとしての逞しさによって、今のフレデリックだからこその強さを感じさせるものになっている。
そして健司は
「ロッキン!音楽大好きっていう人はどれくらいいますか!両手を挙げてくれ!」
と言うと、その音楽が大好きであるという思いを自分たちの音楽にしてきた最新系の曲と言える、代々木体育館で新しいフレデリックの代表曲になった「ジャンキー」が演奏される。こうしてライブで聴くと、楽しくて仕方がない中にも感動がありすぎたあの代々木のライブを思い出してしまう。それくらいにこの曲はもうファンにとっては大事な曲になっているし、そんな曲がロッキンのメインステージで鳴らされているというのは本当に音楽が大好きで、こうしてこの場所にいることができて良かったなと思える瞬間である。
そんなライブの最後を担うのは康司のベースがうねりながらも疾走感を生み出し、それを高橋のドラムが加速させるというセッション的な演奏から突入していった、今やフェスシーン最大のアンセムとなった「オドループ」で、観客は腕を上げたりMVと同じ振り付けをしたりして本当に楽しそうに踊っているのであるが、「愛の迷惑」同様にこの曲も2015年の初出演時に演奏されていた。
でもあの時と決定的に違うのは、もう今のフレデリックはこの曲だけが突出したバンドではないということ。それに並んだり、超えるような曲を次々と生み出してきた。それでも、
「踊ってたい夜が大切なんです
とってもとってもとっても大切です」
というフレーズがより強い意味を持って響くようになってしまったこの数年間だったからこそ、こうした場所の大切さを確かめるようにこの曲を最後に鳴らす。そして健司はまた最後に観客に問いかける。
「音楽が大好きっていう人は両手を挙げてくれ!」
様々な出演者やフェスのTシャツを着た観客が全員両手を挙げている光景を見て、やっぱりこれがあれば大丈夫だと思った。それは音楽への愛をひたすら歌い続けてきてくれたフレデリックのライブだからこそそう思えたのだ。
1.KITAKU BEATS
2.シンセンス
3.オンリーワンダー
4.熱帯夜
5.愛の迷惑
6.ジャンキー
7.オドループ
13:30〜 KANA-BOON [GRASS STAGE]
ずっとGRASS STAGEに出てきたイメージも強いKANA-BOONであるが、実は初出演は他の若手バンドと同じようにWING TENTで、そこからLAKE STAGEを経てGRASS STAGEにたどり着き、そのステージを担ってきたバンドである。そんなバンドの3年振りのロッキンはバンドの新体制で初めてのロッキンにもなる。
なのだが実はフレデリックのライブの終盤から空を黒い雲が覆い始めて遠くの空では雷が光るという「大丈夫か?」という状況の中でのライブはいきなり古賀隼斗(ギター)があの軽快なギターを刻む「ないものねだり」からスタート。一時期よりかなりスリムになったようでいて、髪型がVaundyのようになっている谷口鮪(ボーカル&ギター)は早くも声が出せない我々に手拍子でリズムを任せて、ここにいる全員をKANA-BOONのドラマーにしてしまうのであるが、鮪はやはり痩せたことによって動きや挙動の一つ一つから歌唱に至るまでが実にシャープになったように感じる。それは鮪が健康的な生活を送れている証拠でもあるだけにどこかホッとするのだ。
そんな中で「Torch of Liberty」とアッパーな曲が続くのであるが、KANA-BOONのメンバーとして初めてこのロッキンのステージに立つマーシーこと遠藤昌巳(ベース)がグルーヴィなベースプレイだけではなくて体全体を使って観客を煽るような仕草を見せているというのはこれまでのKANA-BOONのライブにはなかった要素と言える。
だからこそ最新アルバム収録の、
「このステージこそが俺の居場所!」
と言って演奏されたダンスチューンの「マイステージ」も実に肉体的というか、ここにきてロックバンドの持つ衝動のダイナミズムを存分に感じさせるようになっている。
とはいえMCでは小泉貴裕(ドラム)の胸ポケットに猫の刺繍がされていたり、対照的に鮪は犬が3匹ほどプリントされているTシャツを着て可愛さをアピールしたりという緩さは変わらないのであるが、演奏になると「フルドライブ」から文字通りに猛加速していく。曲のBPM自体は変わっていないはずなのであるが、過去最高に速さを感じるように思えるのは今のバンドの状態がエネルギッシュ極まりないということであろう。
そのまま問答無用の名曲「シルエット」へと突入していくという代表曲にして名曲の連打に次ぐ連打は休むこともステージを離れることも許さないし、改めてKANA-BOONがフェスという場で本当に強いバンドだなということを感じさせてくれるのであるが、こうして曲を演奏しているうちに雷が鳴っていたほどの分厚い雲が過ぎ去り、なんと晴れ間すら見えてくるという状態に。JAPAN JAMではめちゃくちゃ雨が降っていただけにやはり雨バンドであることを自認していたが、こうして雲を吹き飛ばしたということは今のKANA-BOONが太陽が似合うくらいに眩しい力を放っているバンドだからと言えるのかもしれない。実際に鮪は
「俺たちが太陽を連れてきたから!」
と自信満々に口にしていた。
その自信があるのも頷けるくらいにバンドのアンサンブルが極まり、古賀のシャープなギターも小泉のパワードラムも、遠藤のうねるベースも、何よりも鮪の力強いボーカルの伸びが、今のKANA-BOONは実は過去最強の状態にいるんじゃないのかと思わせるのが「まっさら」であり、何よりも鮪は本当に歌が上手い。こんなに歌えるボーカリストがまた歌い続けることを選択してくれて本当に良かったなと思うくらいに。
そんな中で鮪は新曲を演奏することを告げる。その新曲「きらきらり」はNARUTOの続編であるBORUTOの主題歌であり、つまりは「シルエット」の続編と言えるような曲。だからこそタイトルからも感じられるようにメロディが煌めいているのであるし、鮪が大好きな漫画であるだけに一世一代の名曲を生み出そうという意識が曲に確かに宿っているし、きっと「シルエット」のように漫画を読むとより深く理解できるであろう歌詞も散りばめているのがKANA-BOONなりのタイアップへの向き合い方であるだけに、NARUTOとBORUTOを一気に読んでみたいなと思う。それは果てしなく長い道のりだけれど。
そうしているうちになんやかんやで暑さすら感じるくらいに晴れてきており、そんな空模様と3年振りのこのフェスの開催を祝うようにして演奏されたのは、この日この後に出演するフジファブリックの金澤ダイスケとともに作り上げた「スターマーカー」で、サビではやはり煌めくようなサウンドに合わせて観客が腕を左右に振る。遠藤がステップを踏むようにベースを弾いているのも実に素敵である。そうして今の編成になって初めてのロッキンで、今のKANA-BOONがロックバンドとして生きている衝動を全放出するようなバンドになった。この日のライブはそれを確かに示すものだった。
しかし自分は鮪が休養した時に、もう毎回フェスに出たりしなくていいから、自分のやりたいことだけをやっていて欲しいと思っていた。今となればそんな自分が思っていた以上に鮪は強い人間だったんだなと思わざるを得ないが、こうして今も最前線に立ち続けることを選んだからこそ、今こんなにも強くて逞しいKANA-BOONの姿を見ることができている。
鮪は最後に先ほどライブを終えたフレデリックと2マンライブを行うことを告知したが、そうしてライブ猛者たちと2マンツアーを回るということができるのも、KANA-BOONがこうした場所に戻ってくることを選んだからだ。なんだか、WING TENTで初出演した時の「凄いバンドが出てきたな」って思った時よりも今の方がKANA-BOONというバンドにドキドキしているし、これからもっと凄いものを見せてくれる予感がしている。そう思えるのがこの上なく嬉しいのだ。
1.ないものねだり
2.Torch of Liberty
3.マイステージ
4.フルドライブ
5.シルエット
6.まっさら
7.きらりらり
8.スターマーカー
14:45〜 ビッケブランカ [PARK STAGE]
実はライブが始まる時間を間違えてしまっており、青空が広がってきて暑くなってきたことで呑気にビールを飲んだりしている間にすでにビッケブランカのライブは始まってしまっていた。
バンドメンバーとともに演奏しているビッケブランカは装飾が施された自身のピアノをサングラスをかけた状態で歌っており、そこからさぁステージ前に出てきてハンドマイクで歌う…というところでサングラスを外そうとするのだが、その瞬間に太陽の光が眩しくて目がやられそうになるという小芝居も挟まれるというあたりのエンタメっぷりはさすがである。
そうしてサングラスを取ってハンドマイクで歌う「This Kiss」のサビではビッケブランカの仕草に合わせて観客の腕が左右に揺れるのであるが、元来ピアノマンである彼がこうして歌に専念できるのは井手上誠(ギター。前日は秋山黄色のメンバーとして出演)らバンドメンバーの存在によるところが大きいのだろうし、キーボードのメンバーに委ねることで自身の歌唱に専念して曲のキャッチーさを最大限に伝えようとしている。
そんなビッケブランカはステージから距離が離れている、客席の丘の上で寝転がったりしている観客に向かって
「君たちも僕のことを見てるの?(笑)
(手を振る観客を見て)あ、見てくれてるのね(笑)ありがとう。
ロッキンは初めて僕がフェスに参加した思い入れの強いフェスです。そこにこうして戻って来れて本当に嬉しいです。でもライブの楽しみ方みたいなものが変わったりしたけれど、今こうしてこのステージに立つことによってみんなの熱量を感じていると、もう元通りだなって思う。それくらいに感じられるものがあります。本当にありがとう」
という真摯極まりないMCにはそれこそステージから距離がある丘の上に寝ている人も含めて大きな拍手を送っていた。ビッケブランカがそう思えたということは、我々がステージへ向ける熱量が声を出せたりしなくても声を出せた頃と同じくらいに伝わっていたということだ。なんだかそれが本当に嬉しかったのである。
するとシュールかつファンキーな「Ca Va?」で観客もバンドメンバーも踊りまくり、ビッケブランカも飛び跳ねたりしながら歌うのであるが、その跳躍力の高さはこの男が意外に運動能力が高いんじゃないかと思わせるし、この曲は聞くと本当に耳から抜けないくらいに癖になる。かといって鯖を食べたくなるかと言われるとそうは思わないけれど。
そして最後はビッケブランカのポップさの極みとも言えるような、野外に実によく似合う「ウララ」が演奏されて、やはり観客はサビで腕を左右に振るのであるが、間奏ではビッケブランカとバンドメンバーたちがあらゆる方向から見ている観客に向かって実に丁寧に手を振る。(井手上がドラムのライザーの上に座り込んでいるのも実に面白い)
そうした挙動やMC、歌声や曲からもビッケブランカの人間性が伝わってくるというか、本当に良い人なんだろうなと思える。それが真っ直ぐに伝わってくるようなライブをビッケブランカはやっている。それは決して激しく魂を燃やしまくるというタイプではなくても、彼がライブアーティストであるということの証明なのかもしれない。
1.Moon Ride
2.アシカダンス
3.This Kiss
4.Ca Va?
5.ウララ
15:45〜 THE BAWDIES [LOTUS STAGE]
元々はこの枠はBiSHが出演する予定だったのが、アイナ・ジ・エンドがコロナに感染したことによって無念の出演キャンセルとなり、代わりに急遽出演が決まったのが代打屋・THE BAWDIESである。ちなみにバンドはかつてもgo!go!vanillasがライブが出来なくなった時にバニラズが抑えていた下北沢SHELTERで代わりにワンマンライブをやるという代打ホームランをかっ飛ばした経験がある。つまりはバンド界の代打の神様・八木裕的な存在である。
「何分急なもんで、ちょっと音を出させてください!」
とROY(ボーカル&ベース)が言ってのサウンドチェックではメンバーは全員ジャケットを着ていなかったというのはあまりに暑かったからかもしれないが、本番ではしっかりスーツを着て出てくるというのがTHE BAWDIESというバンドのスタイルであるのだが、この日はやはりいつもとは違うというのは演奏を始める前にROYは
「アイナさん、BiSHのメンバーやBiSHを楽しみにしていた人たちが少しでも笑顔になれますように!」
と口にしてから爆音ロックンロール「IT'S TOO LATE」を鳴らし始めた。THE BAWDIESがやることは普段と全く変わらない。自分たちのロックンロールをやるということ。だからカバーをしたり、特別な演出を使うというようなこともない。でもこの日は間違いなく普段の自分たちだけではない思いを音に乗せて届けようとしていた。
曲終わりのROYの超ロングシャウトに反応して拍手が起こったりと観客が少しずつ増えてきているのも嬉しいけれど、
「今日は盛大なお祭りだと聞いております!打ち上げ花火の用意はいいですか!皆さんが打ち上げ花火になるんですよ!」
という言葉の後に演奏された、ロッキンでも数え切れないくらいに聴いてきた「YOU GOTTA DANCE」で飛び跳ねまくっていると、本当に今年もロッキンでTHE BAWDIESのライブが見れているという感覚にさせてくれるし、前方エリアで自分の前にいた人がTHE BAWDIESのTシャツを着ていた(タオルはTHE KEBABSだったので自分と同じような音楽が好きだと思われる)のは、急遽決まったとしてもTHE BAWDIESのライブが見れるのが嬉しくてTシャツを着てきたんだろうなと思う。
すでに汗を飛び散らせながらステージを激しく動き回ってギターを弾くJIM、一方でバンドの重要なリフを担うTAXMAN、1人だけジャケットを早くも脱いでシャツ姿になっているMARCY(ドラム)の3人が声を出せない我々の代わりにコーラスを思いっきり歌ってくれているようにすら感じられる「LET'S GO BACK」、歌詞に合わせて指を動かすという仕草を前方エリアの人がやっているのが、ちゃんと曲を知っていて普段からTHE BAWDIESのライブを見ている人がこの日にいるんだなと思えて嬉しい、ブレイクを経ての曲後半で一気にロックンロールサウンドが爆発する「SKIPPIN' STONES」と続くと、
「新曲をやりたいと思います!知らない人からしたら全曲新曲だと思いますけど、我々EPを出して先日までツアーを回っていまして。新曲中の新曲です!(笑)」
というROYのMCもアウェーな場ではあっても割とウケていたような感覚があっただけに、面白い人たちだなというのが伝わってくれていたら嬉しいのであるが、その新曲「STAND!」はガレージロックに振り切った今年リリースの新作EP収録曲。その衝動を炸裂させるような荒々しいサウンドと、アウェーの場をひっくり返そうとするような勢いが、ロッキンに何度も出演してきた、もはやベテランと言える立ち位置であるこのバンドをまるで初出演している若手バンドであるかのように感じさせてくれる。
という雰囲気を一変させるのが、
「初めての方が多いと思うので、先に説明しておきますね。我々はこれから「HOT DOG」という曲の準備に入りますので、しばしお待ちください!」
と言ってメンバーが楽器を置いて始まったこの日の「HOT DOG」劇場は卓子(TAXMAN)とソウダセイジ(ROY)の出会い編という、おそらく1番やってきた回数が多いもの。それはこれが初めて見る人にも1番わかりやすいというのもありつつ、著作権的な問題に触れないネタであるというのもあったんじゃないかと思う。
そんな「HOT DOG」で客席もさらに飛び跳ねまくっている姿を見ると、やはりこの曲は知っているという人も多かったんじゃないかと思う。
そのままお祭り騒ぎなので「T.Y.I.A.」とアッパーなロックンロールを連発するのだが、この曲のコーラスをロッキンでメンバーと一緒に歌いたかったなというのは今回の出演最大の悔いだ。それはどうしようもないことであるし、メンバーが演奏している姿を見て、音を聴くだけでも最高に楽しいのだけれど。
そんなお祭りは楽しすぎるがゆえにあっという間に終わってしまう。MARCYがリズムをキープしながらTAXMANのリフが鳴り響くのはかつてPARK STAGEのトリを務めた時(2010年だったか)にはリリース前の新曲として演奏されていた「JUST BE COOL」。そう考えるとロッキンでのこのバンドの歴史も長いものになったなと思うのだけれども、満員とはいかないまでも多くの観客が飛び跳ねまくる姿がステージから客席を映すカメラによってスクリーンに映るのを見て、確かに伝わるものがあったんじゃないかと思ったし、JIMがいつものようにマイクを通さないで
「ありがとうー!」
と何度も叫ぶ姿を見ていて、その言葉をこっちがバンドに叫んであげたかったと思った。それが出来ないから、今言う。出てくれて本当にありがとう。ROYは最近おなじみの、ステージから去ろうとして立ち止まってポーズを取るというパフォーマンスをして笑いを生み出していたけれど。
代打での出演が決まった時、嬉しかったけれど「もう普通には呼ばれなくなってしまったんだな」と思った。それでもわかっていたことでもある。毎回ワンマンに行っているから、規模が小さくなってきていることも。
でもそんな状況でのライブだったからこそ、かつて初出演のSEASIDE STAGEからPARK STAGE、LAKE STAGEと各ステージのトリを駆け上がり(PARK STAGEでのライブはロッキンに通い続けて見てきた中で5本の指に入るくらいの素晴らしいライブだった)、GRASS STAGEまで辿り着いた。それはTHE BAWDIESがアウェーをホームに変えてきた歴史そのものだった。その頃にライブを見ていた感覚を思い出すことができたライブだった。
ヒーローは遅れてやって来るというのなら、この日のTHE BAWDIESは自分にとってのヒーローだった。
リハ.A NEW DAY IS COMIN'
リハ.I'M IN LOVE WITH YOU
1.IT'S TOO LATE
2.YOU GOTTA DANCE
3.LET'S GO BACK
4.SKIPPIN' STONES
5.STAND!
6.HOT DOG
7.T.Y.I.A.
8.JUST BE COOL
16:45〜 フジファブリック [HILLSIDE STAGE]
2000年代前半、つまりはロッキンの勃興期からどんなことが起こってもこのフェスのステージに立ち続け、昨年のJAPAN JAMでもこのフェスへの思いを口にしていた、ロッキンを担い続けてきたバンドであるフジファブリック。今年は会場も変わったことでHILLSIDE STAGEへの出演。
前日には宮本浩次のバンドメンバーとして出演していた玉田豊夢をサポートドラマーに加えてメンバーが登場すると、日差し対策によってか金澤ダイスケ(キーボード)はサングラスをかけている中で、その金澤のキーボードと山内総一郎(ボーカル&ギター)の歌唱のみという形で「手紙」を歌いあげる。
このステージのキャパを超えるくらいの観客も全員がただただその歌唱にじっと聴き入ることで感じる静寂にも似た空気。それは場所が変わっても、何度もステージに立った「ロッキン」のライブだからこそ、空の上からこのライブを見ているであろう男に誰もが思いを馳せているかのようだった。
それは山内がこのフェスだからこそ叫ぶ
「ジャパーン!」
という言葉もそうだ。それは志村正彦がこのフェスのステージで何度となく叫んできたことでもあるし、志村のそれは彼の師である奥田民生から受け継いだものだ。今はそれを山内が背負っている。それはつまりこのフェスにおける歴史の一部を担っているということであり、それを背負った男としての強さが歌唱や立ち振る舞いにも確かに表れている。
基本的に演奏される曲は近年のフェスでのライブと変わらないので「SUPER!!」での加藤慎一(ベース)と山内がネックを左右に振り、それに合わせて観客も手を左右に振るという一体感も、妖しげなサウンドが歌謡性を感じさせるからこそ山内のボーカルが常に進化を果たしていることを感じさせる「楽園」も見慣れているものであるのだが、それでもやはり「ロッキンでのフジファブリックのライブ」はどんなにやる曲が同じでもやはり感じるものが違うのだ。
それは「夏の曲」と言って演奏された「若者のすべて」が最も顕著だ。ちょうどこの時間は夕方5時。チャイムのようにイントロで金澤のキーボードが鳴る。ロッキンで聴くこの曲はLAKE STAGEにずっと立ってきた志村のことや、その志村が居なくなってしまってからもあのステージに立ち続けてきたこのバンドのことを、何年経っても思い出してしまう。
でも、思い出してしまうのは忘れていないから。きっとこれからも毎年出演するであろうロッキンでのフジファブリックのライブでこの曲を聴けば、志村がこの曲を歌っていた姿や表情を思い出すことができる。きっとそういう思いを持った人がたくさんいるということをメンバーもわかっているはずだ。
でもそうした思いは決して後ろ向きな、ずっと引きずっているというものではない。フジファブリックは自分たちの活動によって前に進み続けることの意味を示してきたバンドだ。だから山内は
「僕らが皆さんの居場所になります!」
と宣言し、ここにいる人のこれからの未来に光が射しますようにという願いを込めて「光あれ」を演奏するのだ。ハンドマイクで歌う山内が手を振る仕草に合わせて観客も手を振るという光景がこの上なく美しいのはもちろんのこと、山内はステージサイドのカメラに寄っていってカメラ目線を向けて笑顔で歌う。こんなに強い姿を見せられたら我々が前を向かないわけにはいかない。最後に山内が再び
「ジャパーン!」
と叫んだのを見て、本当に強い人間たちによる強いバンドだなと思った。
志村が歌っていたライブも、山内が歌うようになってからのライブも、とりわけ3人でLAKE STAGEのトリを務めた時に山内が最後に
「忘れて欲しくないメンバーがいます。志村正彦!」
と紹介した時も。忘れることができない名場面をこのフェスで作ってきたフジファブリックのロッキンの物語はひたちなかから蘇我に場所が変わっても続いていく。その姿に我々が力を貰い続けている限り。今年のこのライブだって、これから何年経っても思い出してしまうんだろうな。
リハ.夜明けのBEAT
1.手紙
2.SUPER!!
3.楽園
4.若者のすべて
5.光あれ
17:25〜 My Hair is Bad [LOTUS STAGE]
アリーナツアーを敢行した今年はMy Hair is Badにとって大きな変化をもたらした1年になった。ミュージックステーションやサブスクの解禁という新たな挑戦。それが結果的にたくさんの人に届いてたくさんの人に求められるようになったことを示すように、空が青から薄らと色を変えてきているLOTUS STAGEの客席は満員である。
メンバーが出てきてのサウンドチェックで「優しさの行方」を演奏して、集まった観客を唸らせると3人は捌けることなくそのままステージ上で開演時間を待ってから本番へ。
するとこの日は珍しく椎木知仁(ボーカル&ギター)がギターを弾きながら
「はじめまして。My Hair is Badです。俺は新潟県上越市に生まれ、夏は野球のボールを追いかけて冬は雪が積もるような街で…」
と自身の生い立ちを語るというスタート。この語り自体はおなじみであるが、そこから始めるというのは実に珍しいし、それはこの語りをライブ途中に挟むことがない内容になるということでもあると言える。
なので椎木はその語りから繋がるようにして「ドラマみたいだ」を歌い始めると、ステージ前に出てきてギターを鳴らすのであるが、
「ロッキン、ドキドキしようぜ!」
と言ってから演奏されたおなじみの「アフターアワー」と続くと、椎木のギターも山本大樹のベースも山田淳のドラムもこの日最大級の爆音でこちらに届いてくる。3人の音しか鳴っていないシンプルなスリーピースサウンドだからこそそのサウンドはよりダイレクトにこちらに届いてくるし、それをこんなにも衝動的に届けてくれるのだから拳を振り上げざるを得ない。それくらいに今のマイヘアのライブはこれまでを更新する熱さに満ちている。
そんなマイヘアの持つメロディの美しさと、ラブソングでありながらもそこら辺の凡庸なラブソングのものとは全くレベルが違う物語を描く椎木の作家性が炸裂している「グッバイ・マイマリー」から、
「今はもう何も考えずにこの曲を歌える」
と言って歌い始めたのは「ブラジャーのホックを外す歌」としてミュージックステーション出演時に広まった「真赤」。当然ながらステージは真赤な照明に染まる中で椎木はギターを掻き鳴らし、山田はシンバルをぶっ叩く。ただインパクトの強い歌詞を歌うバンドではないロックバンドのカッコよさがこのバンドのライブからは確かに感じられる。
そのままこの日の最速を更新するかのようなショートチューン「クリサンセマム」で山本がステージ前に出てきてポーズを決めるようにしてからベースを鳴らすと、一気にサウンドがハードかつラウドになっていく「ディアウェンディ」では椎木は
「今が最高、最新、1番カッコいいMy Hair is Badだ!」
と目元でダブルピースを作りながら叫ぶと、
「このステージの名前の「LOTUS」の意味知ってる?ギリシャ神話に出てくる禁断の果実なんだって!一度食べたら止まらなくなるような。それって音楽そのものじゃないか!
マリファナでもコカインでもLSDでもMDMAでもない、これが音楽っていう最高なドラッグだ!」
と淀みなく次々と言葉を放ち、その言葉がバンドの演奏をさらに加速させていく。個人的にはこの曲での山本が笑顔でポーズを決めるのも椎木の言葉に並ぶ見どころの一つだと思っている。
そんな禁断の果実が実るこのステージの激しさと暑さを更新するような曲から一転して、椎木は穏やかにギターを爪弾くようにして「味方」を歌い始める。これまでもフェスでも「いつか結婚しても」などの壮大なメロディを持った曲を演奏してきたバンドであるが、
「きっとこれからも僕は正義にも悪にもなれないけど
誰よりも君の味方だ」
「君が笑えば なにもいらない
君がいれば 僕は負けない」
というフレーズはこうしてこのバンドを前にしている人の誰もが歌って欲しい言葉であり、そんな人がいるからこそバンドが歌える歌詞だ。山本のアウトロでのコーラスを含めて、こうした曲にこそこのバンドの優しさを感じられると思うし、そうした面も、素直な面も激情的な面もステージで隠すことなく見せてくれるこのバンドのメンバーたちは本当に人間らしいと思う。
そんな曲の後に椎木は
「今1番歌いたい曲。この曲を歌いに来たと言っても過言ではない」
とまで言い切ってから最新アルバム「angels」収録の「歓声をさがして」を演奏する。音楽を見失いそうになる数年間だったけれど、この曲は一つの出口を示してくれているし、だからこそこの曲を歌い鳴らすメンバーの表情は実に穏やかだ。「フロムナウオン」を演奏しないのもそういう理由だろうし、それはJAPAN JAMでも演奏していかなかっただけにこの場所はマイヘアをそうした心境にしてくれる場所なのかもしれない。そんな場所が来年には探すことをしなくても歓声が響いている場所だったらいいなと思う。
そんなライブの最後に演奏されたのは「夏の曲」と言って演奏された「夏が過ぎてく」。それはこの季節じゃないと聴けない、マイヘアの真髄のような曲。このライブがあっという間に過ぎ去ってしまったように、今年の夏も音楽を求めていろんな場所に足を運んでいる間にあっという間に過ぎていくんだろうなと思いながらステージから目線を上に上げるとまだ明るい。もう18時を過ぎているというのに、こんな時間になってもまだ明るいだなんて。
今でもこのフェスのWING TENTにマイヘアが初めて出演した時のことをよく覚えている。ずっとロッキンオンジャパンを読んでいたから憧れのフェスだったことを語りながら、椎木は
「1番デカいステージまで行ったら、ステージを飛び降りて客席に突入する」
と言っていた。実際にひたちなかでも1番デカいステージであるGRASS STAGEに立ったのだが、その時に椎木は客席に突入することをしなかった。そうしなくて本当に良かったなと思うのは、このフェスのルールを守り続けてきてくれたことで、我々は3年も期間が空いても、場所が変わってもこうしてこのフェスでマイヘアのライブを見ることができているからだ。
リハ.優しさの行方
リハ.カモフラージュ
1.ドラマみたいだ
2.アフターアワー
3.グッバイ・マイマリー
4.真赤
5.クリサンセマム
6.ディアウェンディ
7.味方
8.歓声をさがして
9.夏が過ぎてく
18:05〜 PEOPLE 1 [HILLSIDE STAGE]
まだライブ経験3回目にして今年の春にJAPAN JAMに出演し、そこで鮮烈なフェスデビューを果たした、PEOPLE 1。その際に渋谷陽一も
「このバンドの出演を発表した時にたくさんの人が喜びのコメントを書いてくれた」
と言っていたが、そのライブがこうしてまた夏にこの会場に戻ってくることに繋がったのである。
サポートのギター、ベースを加えた5人編成で、向かって下手側から帽子を被った姿が何度見てもハマ・オカモトに似ていると思ってしまうDeu(ボーカル&ギター&ベース)、見た目からして逞しさを増したように見えるIto(ボーカル&ギター)、キッズのような出で立ちのTakeuchi(ドラム)が前列に並ぶと、Itoが飛び跳ねるようにしてキャッチーなメロディを歌う「魔法の歌」からスタートするのであるが、JAMの時のライブ開始時の緊張感はどこへやらというくらいにこの日はもう最初から堂々としているというか、もう楽しみきってやる!というメンバーの思いがその姿に溢れ出ている。
Deuがハンドマイクでメインボーカルを担う「怪獣」「スクール!!」という曲においても、JAMからの3ヶ月でこのバンドに何があったんだろうかと思うくらいに、このバンドは急にライブバンドとして化けたなということが瞬時にわかる。元からファンキーな曲であるのだが、JAMの時はまだどんなもんかと大人しく見ていた感も強かった観客もこの日は踊るしかないだろ!とばかりに踊りまくっている。それはサポートメンバーたちもガンガン前に出てきて演奏したり、ItoとDeuもステージ上で暴れまくっているかのように激しく動きながら歌っているというステージ上の熱量が観客側に伝わっているからであり、もうこの時点で楽しさがJAMの時とは段違いだ。
それはこのバンドがJAM以降も対バンを含めてライブを重ねてくるという日々を送ってきたからであり、実際にJAMの時には新曲として演奏されていた「銃の部品」の華やかさすら感じるポップサウンドが完全にライブに欠かせないものとして馴染んでいる。何よりもItoが激しい動きを見せるだけではなく、その挙動がしっかりと歌に籠るようになっている。全然知らない人がこのライブを見たら、まだ数えられるくらいしかライブ経験がないバンドとは全く思わないだろう。
すると一転してDeuが椅子に座ってムーディーな空気感になる中で
「僕はこの日ここで歌うためにこの曲を作ったのかもしれない」
と言って「113号室」を歌い始めるのだが、シンセベースのリズムとサウンドを生かしたこうした激しさとは対極と言えるような曲の表現力もこのバンドは見事に獲得している。
そしてJAMの時に「この曲はこれからロッキンオンのフェスのアンセムになっていくかもしれない」と思わされた「常夜燈」が暗くなったこの会場に灯りを灯すかのような暖かさを持って鳴らされる。ああ、やっぱりこの曲はそうした存在になっていくんだろうなと改めて思ったのは、またJAMの時のようなデカい規模のステージでこの曲を聴きたいと思ったからだ。まだJAMの時は「さすがにステージがデカすぎるな」と思ったのだが、むしろ今はあの規模の方が似合うんじゃないかと思うほど。
それを証明するかのようにItoとDeuのツインボーカル的な歌唱による「エッジワース・カイパーベルト」はもはやステージ上も客席も祭りのピークであるかのような凄まじい盛り上がりっぷりを見せる。きっと各地のライブハウスで見てきた景色がこの曲をここまでライブ映えするものに育て上げたんだろうなと思うし、何よりもメンバー全員が本当に楽しそうに音を鳴らしている。経験が乏しいからライブが怖いなんて全く思ってないどころか、もっともっとこうしてライブをやりたい、そして目の前にいてくれている人と繋がりたいという思いが音からも姿からも溢れ出ている。だからこそ熱狂の中にも感動にも似た感情が芽生えているのを確かに感じていた。
全くMCを挟まないというのもひたすらに曲を演奏しまくりたいという思いからであろうけれど、そんなライブの最後に演奏されたのはファンを大衆と称するこのバンドによる「大衆音楽」。それはつまりこのバンドはやはり誰よりも今目の前にいる人に向けて音を鳴らしているということだ。Takeuchiの強靭すぎるビートによって狂乱的なサウンドの楽しさに包まれながら、もう完全にこのバンドのポップソングに夢中だと思った。何ならこの日の裏ベストアクトと言っていいくらいに超絶進化を遂げたことをわずか3ヶ月ぶりのライブでPEOPLE 1は証明していた。
たまにツイッターで「このバンドのライブを見て欲しい」と言われることがある。JAPAN JAMの時も今回も「PEOPLE 1を是非見て欲しい」という声をよくいただいた。そう言ってくれた人たちはこのバンドのライブの凄まじさをもう知っていたからこそ、自分にそう言ってくれたのだと思うけれど、もうそう言われなくてもこのバンドのライブをすぐに観に行きたい。それくらい、本当にこのバンドの大衆音楽に夢中になってしまっている。
1.魔法の歌
2.怪獣
3.スクール!!
4.銃の部品
5.113号室
6.常夜燈
7.エッジワース・カイパーベルト
8.大衆音楽
18:45〜 THE KEBABS [PARK STAGE]
普段からこのブログやツイッターを見てくれている人がもしいるのであれば、自分が佐々木亮介というa flood of circleのボーカリストのことが大好きで仕方がないことは理解していただけていると思う。そんな佐々木亮介がUNISON SQUARE GARDENの田淵智也(ベース)らと組んでいるバンドがこのTHE KEBABSである。
なのだが、大好きだからこそ、リハでステージに現れて
「俺もあいみょん観たかった〜」
と言っている亮介の姿を見て驚いた。派手なパジャマ姿であるのはフラッドの革ジャンとは違うTHE KEBABSの時の衣装であるのはわかっているのだが、髪色が金から緑色混じりになっていたからだ。ここにきての亮介のこの自由っぷりには自分もまだまだそういうやりたいと思ったことを自由にやっていいんだなと思わせてくれる。ちなみに田淵は
「俺もあいみょん見たかったけど、PEOPLE 1見れて嬉しかった〜」
とさすがの若手チェックっぷり。それがユニゾンが対バンイベントを主催する時にまだあまり知られていない若手バンドを呼ぶというラインナップに繋がっているのかもしれない。
そんな田淵はサウンドチェック時はサングラスをかけたりしていたのだが、本番ではいつも通りに外してライブに臨み、おなじみの「THE KEBABSのテーマ」で新井弘毅(ギター)がリフを刻み、鈴木浩介(ドラム)が激しいビートを刻む。このドシンプルなTHE KEBABSのロックンロールが初めてロッキンで、この蘇我の地で響き渡り、亮介はサビで高く飛び跳ねると同じように観客も飛び跳ねまくる。難しいことを全く考える必要のないTHE KEBABSのロックンロールはこうして頭を空っぽにして楽しむことができる。
鈴木と田淵のリズムが一気に加速する「恐竜あらわる」、おそらくはアニメ化が決定している某人気漫画から着想を得たと思われる、新井のギターのシャープさが炸裂する「チェンソーだ!」とタイトルを並べると実にアホっぽいけれど、その発想をダイレクトに音や曲にするというのもまたTHE KEBABSなりのロックンロールだと言えるだろう。
だし、何よりもTHE KEBABSはメロディが良い。それはa flood of circleとUNISON SQUARE GARDENのソングライターが曲を作っているのだから当然と言えば当然であるが、
「ロバート・デ・ニーロの袖のボタン」
という、何でこんな歌詞のサビ?と思うようなフレーズをこんなにもキャッチーかつロックンロールに昇華できるミュージシャンは他にいないだろう。亮介は右腕を高く掲げてそのロックンロールを歌うために持って生まれた声を高らかにこの蘇我の夜空に響かせる。近年の亮介はどれだけ酒を飲んでも素晴らしい歌唱を聞かせてくれている。
そんな亮介がギターを持つと、ここまでのストレートなロックンロールサウンドから聞かせるタイプのバラードと言っていいサウンドになるのは、サビでは田淵が普通に上手いボーカルを聞かせる「ラビュラ」なのだが、これまでにこの曲を聴いてきたライブでは
「今年の夏は海に行けなかったし
山にも行けなかったし
お祭り そもそもなかったし」
というフレーズがコロナ禍での夏を過ごさざるを得なかった、フェスというお祭りすらもなかった夏のテーマ曲として響き、その切なさに涙せざるを得なかったのが、この日は亮介は最後に
「今年の夏は海に行こうぜ 山にも行こうぜ!」
と叫んだ。それはこうしてお祭りが戻ってきた今年の夏だからこそ加えることができたもので、今までこの曲を聴いてきた時とは違った意味で涙が出てきてしまった。そのお祭りをこのバンドたちと過ごせているのだから。
すると「THE KEBABSは忙しい」から再びロックンロールサウンドに転じ、新井も荒ぶりながらギターを弾き、その横に田淵が立ったかと思えば亮介は新井の両足の間から頭を出している。この自由っぷりこそTHE KEBABSのライブの楽しさであるが、新井はSerial TV dramaで、鈴木はART-SCHOOLで何度もひたちなかのロッキンのステージに立ってきた。そんな2人が年月を経て亮介と田淵と一緒にロッキンのステージに帰ってきたのだ。それは亮介と田淵がこのバンドを始める時に望んだことの一つなのかもしれない。喋ることはなかった2人はこの景色をどう見ていたのだろうか。
そんな4人のライブはクライマックスへ。亮介も田淵もリズムに合わせて飛び跳ねまくりながら、亮介は腕を掲げて伸びやかなボーカルを響かせる「ジャキジャキハート」がやっぱりこのバンドの曲は最高にキャッチーだなと思わせながら、ここからまたどこまでも遠くまで行けると思わせるような力を我々にもたらしてくれる。
それでもまだライブは終わることはなく、亮介は
「ROCK IN JAPANに何しに来たの!?ロックンロールでしょ!」
と思いっきり叫んでから、再び「THE KEBABSのテーマ」を演奏するのだが、最初とは全く歌詞が違っていて、鈴木にやたらと絡みながら歌うというバージョンになっていた。そうした自由さを含めて、THE KEBABSは、亮介はロッキンの「ROCK」の部分を自分たちが担って守っていこうとしている。その姿勢こそが何よりもロックンロールなのだ。あまりにも会心過ぎたPARK STAGEのトリのTHE KEBABSのライブ。もはや佐々木亮介という男のことを自分は「ロックンロール」と呼びたいと思うほどに。
でも、来年はTHE KEBABSだけじゃなくてa flood of circleでも呼んでくれないとな、と出演が発表された時からずっと思い続けている。ユニゾンは多分来年は普通にメインステージに立っているから。
1.THE KEBABSのテーマ
2.恐竜あらわる
3.チェンソーだ!
4.ロバート・デ・ニーロ
5.ラビュラ
6.THE KEBABSは忙しい
7.ジャキジャキハート
8.THE KEBABSのテーマ
19:25〜 King Gnu [LOTUS STAGE]
中止になった昨年もトリとして出演がアナウンスされていた、King Gnu。そのリベンジとも言えるライブであるし、3年前はまだPARK STAGEに出ていたことを考えるとこのフェスがなかった期間で日本トップクラスのバンドになったということである。
夜になって完全にステージが闇に包まれる中で不穏なSEが響くと、やんちゃな見た目の勢喜遊(ドラム)が力強いビートを刻み始め、そこにメンバーたちが合流してくると、SEのサウンドをそのまま引き継ぐように不穏にアレンジされた「Slumberland」が始まり、常田大希(ボーカル&ギター&キーボード)が拡声器を持って歌い始めるといきなりの特効が炸裂し、ステージは濃いスモークに包まれていく。その不穏な空気とサウンドはまさにディストピアと化している今の日本の情勢をサウンドと視覚の両面で表しているかのようである。
そのステージを覆うスモークがさらに濃くなり、メンバーの姿が見えなくなるくらいになる中で常田がギターに持ち替えたのがわかるサウンドとどっしりとした思い勢喜と新井和輝のベースによるリズムが響くのは「飛行艇」でより太ったように見えなくもない井口理(ボーカル&キーボード)はその美しい声を存分に響かせながら観客の腕を高く掲げて揺らせる。もう完全にこの段階でこのバンドの世界観がロッキンというフェスを飲み込んでしまっているのがわかる。
さらに常田がギターをカッティングしまくるサウンドが心地良くもカッコいい「Sorrows」から、人気アニメのタイアップ曲としてこのバンドの名を一段上のステージにまで引き上げた「BOY」と、前半はアッパーな曲を連発していくのだが、そのサウンドを支えるリズム隊の躍動感は凄まじいものがある。さすがいろんな場所でそのリズムを響かせては腕を磨いている2人である。
そんな前半で早くもバンドの転機となった大ヒット曲の「白日」が演奏され、井口の美しいハイトーンボイスが響き渡るのであるが、この曲がリリースされたばかりの頃に出ていたフェスではこの曲が終わったらステージを移動する人も結構いたりしたのだが、今は全くそんな人がいないというのはこの曲の後にも名曲や代表曲が待っているのをここにいる誰もがわかっているからであるし、何よりこの日のトリとしてのライブだからだろう。
その「白日」からさらに深い深層部分まで潜っていくように常田がピアノを弾いて井口がよりハイトーンかつ痛切な感情を音に乗せるように歌う「The Hole」、さらにはここまでは夜ということもあって薄暗い中での演奏だったのが、タイトルに合わせるように照明がフレーズごとに変わっていく「カメレオン」と聴かせるタイプの曲が続く。持ち時間が長いとはいえ、日本最大規模のフェスのステージでこうした盛り上がるというのとは真逆と言っていいような曲を連続で演奏できるというあたりにこのバンドが時代の勝者になった理由が感じられる。ただただひたすらに楽曲とライブの力でここまで来たバンドということである。
そんな空気を切り裂くように響き渡るのがあまりにも音の強さも手数の多さも凄まじすぎてあんぐりしてしまうくらいの勢喜のドラムソロなのだが、そこから「Vinyl」に繋がるというのはフェスに出始めた頃からの定番の流れであるが、新井のステージ上で踊るような、舞うような演奏も井口のボーカルもドームクラスに立つようになったバンドの力が曲の持つ力をより引き上げているかのようである。
そんな井口は
「あ、喋る喋る(笑)」
と言って喋り出すだけで緊張感すら感じるくらいに張り詰めた空気のライブを和ませてくれるのであるが、前月のNUMBER SHOTでは新井がコロナに感染して新井の演奏する映像を流してのライブだったのが、この日はようやく4人で揃ってライブができることで、
「落ち着きすぎて家にいるみたいになっている(笑)」
と、このステージでこれだけ凄まじいライブをやりながらも口にできる井口はやはり只者ではないなと思う。
その井口のハイトーンボーカルがサビの締めの
「何を信じればいい?」
のフレーズで極まる「Prayer X」から、ここまでの漆黒の闇の中でのライブをカラフルな照明が一変させる「Teenager Forever」では井口がステージ前まで出てきて、ただ上手いだけではなくてロックバンドとしてのエモーションを思いっきり込めた歌唱を響かせる。それは実は銀杏BOYZなどに大きな影響を受けている井口だからこそこのバンドにもたらすことができるロックさであるのだが、その井口の熱量によって観客の興奮のボルテージはさらに向上していく。
それが常田のボーカルにも乗り移るかのような「Flash!!!」ではまたしてもステージが濃いスモークに包まれて、メンバーの姿が見えなくなっていく。その際に井口が何らかのパフォーマンスを準備しているんじゃないかと思ってしまうが、かつてははっちゃけまくっていたこの曲の間奏でもあくまで観客を煽るのみというくらいにパフォーマンスが洗練されてきている。
そんなバンドはまたしても名曲を生み出したばかりであり、その配信リリースされたばかりの新曲「雨燦々」がここで演奏される。照明などの演出がまさに雨を思わせるものになっているのだが、それでもこの日雨が降らなくて良かったと思えるのは視界を遮ることなくこのバンドが演奏している姿を見ることができるからであるし、「傘」という同じように雨をテーマにした曲もあったけれども、今までの曲とは全くタイプの曲を生み出しているというのが本当に恐ろしく感じるし、何よりもどれだけ引き出しがあるんだというくらいのメロディの美しさ。これはもはやタイトルとしても賛美歌のように感じられるような。
そんなライブも終わりの瞬間が迫ってきている。井口は
「今日出演することができて本当に嬉しかったです。ありがとうございました!」
と挨拶をすると、ラストは「逆夢」からの「一途」という映画「呪術廻戦」のテーマソングの2連発。劇場で映画を見た時のエンディングでのこの2曲が続けて流れた時のゾクっとするようなカッコよさをライブという場で何倍にもして感じさせてくれるこのコンボは本当にKing Gnuの数あるタイアップ曲の中でも最も幸福な結果と成果をもたらしたものになったんだなと思うくらいの圧巻さ。全てが代表曲かつ名曲でしかなくて、それを何倍にも増幅させる演奏ができるという、このバンドがこのフェスのトリにまで辿り着いた理由が見れば絶対にわかるような凄まじいライブだった。
それは勢喜のドラムの強さ、新井の踊るようなベースの華麗さ、常田のギターと歌唱のロックさ、井口のエキセントリックでありながらもキャッチーさを備えた曲をさらに大名曲に引き上げる歌唱という異次元レベルのミュージシャンが揃ったこのバンドが、その名の通りに王としてシーンに君臨することを示すようなものだった。
でもきっとこのセトリはフェスだからこそのものでもあるはず。果たしてワンマンではどんな風に驚かせてくれるのか。それを体験してみたくなった。沼っていう表現は安易すぎて使いたくはないが、それでも使わざるを得ないくらいに引きずり込まれそうになっているのがよくわかる。この日、King Gnuはこのフェスのトリを担ってきたバンドたちに名実ともに肩を並べる存在になったのだ。終演後に打ち上がった花火はその祝福であるかのようだった。
1.Slumberland
2.飛行艇
3.Sorrows
4.BOY
5.白日
6.The Hole
7.カメレオン
8.Vinyl
9.Prayer X
10.Teenager Forever
11.Flash!!!
12.雨燦々
13.逆夢
14.一途
20:30〜 四星球 [HILLSIDE STAGE]
そのKing Gnuのライブ後に打ち上がる花火を立ち止まって眺めることなくHILLSIDE STAGEへ駆け出していたのは若干時間が押し気味だっただけにクロージングアクトが始まりそうになっていたから。3年前にはBUMP OF CHICKENの真裏のLAKE STAGEのトリを務めた、ロッキンが誇る最強のクローザー、四星球がこの日のクロージングアクトである。
なのでステージに着いた時にはすでにメンバーが登場していたのだが、北島康雄(ボーカル)の口ぶりから察するにこの日のライブは2020年にタイムスリップしたという設定らしく、U太(ベース)の出で立ちは確かにその年にブレイクした瑛人の「香水」のMVのコンポラリーダンスを踊る人であるのだが、まさやん(ギター)とモリス(ドラム)は見てもよくわからない中で「鋼鉄の段ボーラーまさゆき」からスタートし、観客はエアギターをしたりしながらその場をグルグルと回るという今のライブのルールを守った楽しみ方をしながらタイトル通りにまさやんがフィーチャーされるのかと思いきや、
「前方エリアの奴が遅れて来るな!早く来て待っとけ!」
と前方エリアを当てた人がKing Gnuを見終わってから遅れて来たのを見つけた北島は御立腹で叫び、早くも演奏された「クラーク博士と僕」ではまさやんがギターを何度も空中に投げてキャッチし、北島は段ボール製のハム焼きを持ってまさやんをブン殴りまくる。そんな中でもみんなが早く帰れるようにとこの蘇我スポーツ公演の地図を用意したりと、優しいんだかバイオレンスなんだかよくわからない。
最終的にはまさやんがハム焼きで北島をブン殴って北島がステージに倒れ込むという形で曲が終わるのだが、その北島が倒れている姿を見たまさやんは
「あれ!?あれ、産まれたての仔馬じゃない!?」
と、その産まれたての仔馬が立ち上がるための新曲である「UMA WITH A MISSION」を振り付けを踊りながら歌う。この日は本家であるMAN WITH A MISSIONも出演していただけにもしかしたらコラボもあるかなと思ったりしたのだがそれはなく、京都大作戦などではやたらと時間をかけて立ち上がっていた仔馬こと北島もこの日はすんなり立ち上がるのだが、この曲に時間を使わなかった理由は
「どうしても演奏したい曲があるから」
というものなのだが、その曲はなんとこの日出演キャンセルになったBiSHの「BiSH -星が瞬く夜に-」。この曲を完璧に演奏できるメンバーの鉄壁の演奏技術あってこそできるパフォーマンスであるが、振り付けを観客が完璧に踊っているあたりに今のBiSHがどれだけたくさんの人に愛されているのかということがよくわかる。
実際にこの日はBiSHのTシャツを着た清掃員の方もたくさん会場に来ていて、1番見たかったであろう存在がキャンセルになっても他のバンドのライブで楽しんでいる姿が印象的だった。それはBiSHがいろんなフェスに出演していろんなバンドと対バンしてきたからこそ、他のアーティストのライブを楽しむということが清掃員の方々に浸透しているんじゃないかと思ったし、観客だけではなくて出演者からも愛されてるのもそうした理由だろう。
そんな飛び道具のような正攻法を展開しながら北島は
「このステージのHILLSIDEの意味知ってる人います?丘の中腹っていう意味なんですよ。でも我々中腹で止まるつもりなんてありません!HILLTOPまで辿り着きたいと思ってます!」
と高らかに宣言して「妖怪泣き笑い」では観客を一旦座らせてから一気にジャンプさせる。何なんだろうかこの楽しさと感動は。先月の都内でのワンマン、やっぱり行けば良かったかなと思ってしまうくらいに、凄いライブを見てきた1日が四星球に持っていかれようとしている。それを確かなものにするようにメンバーはこの日使った小道具のパーツを解体してホワイトボードに
「ロッキン大好き」
という文字を作るのであるが、普段ライブが終わった時にやるそのパフォーマンスを今やるのは早くないか?と思っていたら、U太が蹴りを繰り出すかのように激しいアクションを見せ、まさやんは叫ぶようにして歌う「薬草」を、エンタメの力でここにいる人に明日からの生活を生き抜いていくための活力を与えるべく演奏すると、
「ロッキン大好き」
の文字の一部が剥がれ落ちて、それを修復するとなぜか
「ローション大好き」
になり、ステージにはビニールプールと大量のローションが運び込まれてまさやんがローションまみれになるという笑劇のラスト。
「来年から呼ばれなくなったらこれのせいです(笑)」
と北島は言っていたが、フェスのスタッフTシャツを着た人たちも袖で爆笑しながらその様子を見ていた。それくらいに誰しもを笑顔にしてくれるバンドが出禁になるわけがない。むしろこれからも最強のクローザーとしてこのフェスに君臨し続けていくということを示すような、全てを持っていくようなライブだった。北島は
「今日、目をクロージングする時に思い出すライブがこれだからクロージングアクトなんです!」
と言っていたが、もはやクロージングアクトというよりこの日の、いや一週目のロッキンの大トリはこのバンドだったのだ。
メンバーがステージを去っても客席からはアンコールを求める拍手が鳴り続けたのが、北島はそれに応えるために出てきたのかと思いきや、
「メンバーの1人があんなにローションまみれになってアンコールできるわけないやろ!(笑)」
と言ってアンコールはやらずにステージを去っていく。それでもなおもアンコールを求める手拍子が響くとまた北島が出てきて、
「お前らはアホかー!(笑)」
と律儀にツッコミを入れてくれた。いや、それくらいに四星球のライブがもっと見たいくらいに素晴らしいクロージングアクトとしてのライブだったんだよってことはきっと伝わったはずだ。
四星球はまだロッキンに出るようになってからは年数は経っていない。それでもBUMPの裏という誰もやりたくないような位置を立候補したりと、すでにロッキンへの貢献度は計り知れないバンドだ。それくらいにこのバンドは日本で1番巨大なフェスをコミックバンドとして背負おうとしている。それはきっとたくさんの人の思いを背負うことは重荷ではなくて自分たちの力になることをわかっているバンドだからだ。もう来年はメインステージのトリとしてライブを見たいとすら思えるくらいにこの日の全てを掻っ攫っていってしまった。
1.鋼鉄の段ボーラーまさゆき
2.クラーク博士と僕
3.UMA WITH A MISSION
4.BiSH -星が瞬く夜に-
5.妖怪泣き笑い
6.薬草
10:30〜 ハルカミライ [GRASS STAGE]
10時くらいに、まだまだ始まるまで時間があるし、暑くなってきたから冷たいものでも食べるかと思って夏フェスおなじみのスイーツであるいちごけずりを呑気に食べていたら、すぐ裏のGRASS STAGEからは早くもサウンドチェックと称したメンバーによる本気の演奏が始まったので慌てて食べてからステージへ。先日に地元の八王子のホールで2daysライブを終えたばかりのハルカミライがついにGRASS STAGEというロッキンのメインステージのトップバッターである。
このGRASS STAGEではロッキンオン社長の渋谷陽一の朝礼がある。そこで渋谷陽一は前日に駅に機動隊が出動してもしもの際に備えていたというが、そんな必要が全くなかったくらいに参加者のマナーとモラルが良かったことを褒めていたのだが、そんなルールをちゃんと守る若者としてこのハルカミライを紹介する。
「ずっとこのバンドが好きで、うちのフェスに入れろって言ってきたから、ロッキンオン内では社長のバンドって言われてる(笑)」
というのはハルカミライのファンとしても、渋谷陽一のファンとしても実に嬉しいことであるが、確かにハルカミライはまだここまでの存在になる前のCDJ18/19からロッキンオンのフェスに出ていた。それも社長のゴリ押しだったということだろうか。
そうした紹介(まさか渋谷陽一の紹介でハルカミライが登場するライブを見れるなんて全く思ってなかった)から、おなじみの新世界リチウムの「喝さい」が流れて小松謙太(ドラム)、関大地(ギター)、須藤俊(ベース)の3人が先にステージに登場し、最後におなじみのフラッグを持った橋本学(ボーカル)が登場すると、
「今日、20曲やるから(笑)」
と口にしてから「君にしか」「カントリーロード」の鉄壁の流れのオープニングとなり、関はアンプの上に立ってから大ジャンプを決める。その光景を映した写真があったならすぐさま公開してほしいくらいに鮮やかな姿だったのだが、間奏でのブレイクで橋本は
「昨日、ワンピースの映画見てきた!」
と発表すると須藤も
「今からネタバレしまーす。聞きたくないやつは耳を塞げー。ルフィとナミが結婚しまーす」
と嘘でしかないようなことを口にすることによってネタバレを回避してみせる。その全てが実に楽しそうというか、それは野外の開放感によってもたらされているものもあるのかもしれない。
すでにリハでも2回演奏されていたことによってこの日3回目の「ファイト!!」から一気にパンクに振り切れていくスイッチが入ると、「俺達が呼んでいる」では須藤と関が広いステージをスライディングしたり、橋本はステージ左右に伸びる通路の柵に跨って歌ったりとやりたい放題であるが、それでも決してルールを破ることはないというのはさすがであるし、それはハルカミライにとってはキチンとルールを守ることが出来る人ほどカッコいいという価値観によるものだろう。
だからこそ橋本は
「ここが世界の真ん中!」
と高らかに宣言した「春のテーマ」の曲中に客席の一部を指差して、
「兄ちゃん、あんたはライブを楽しむプロだ。だから撮影するのは撮影のプロのカメラマンの人に任せてくれ」
と言った。前方エリア(しかも多分かなり最前に近い位置)で堂々とライブを撮影するのもそれはそれで凄い気もするが、その人を決して悪者にするように叱ったりはしないというあたりが本当にハルカミライのメンバーの人間性が出ているし、それを鳴らしている音からも感じられるからハルカミライの音楽やライブが好きなのだ。自分もこういう人間になることができたらな、とメンバーよりも年上でも思ってしまう。
目標を20曲に設定していることによって中盤でも容赦なくショートチューンを連発するのであるが、
「夏の曲をやります!」
と言って演奏された「夏のまほろ」での晴れているのに(橋本は「太陽呼んじゃった!」と狙って奇跡を起こしたように口にしていたが、それもこのバンドのライブを見ると本当にそう思える)微かに雨が顔に当たっているというシチュエーションのあまりの見事さ。35°Cに届きそうとまではいかないけれど、このバンドのライブが我々をそれくらいに暑くしてくれる。
さらには橋本のボーカルの伸びやかさが青い空に突き刺さっていくかのような「ウルトラマリン」では
「1番綺麗な君を見てた」
のフレーズに合わせて観客が一本指を突き上げるのだが、まさにこの光景こそが1番綺麗なものであるかのようだ。
さらにメンバーが入り乱れまくりながらコーラスをしまくる「PEAK'D YELLOW」ももはや完全にフェスにおけるアンセムと呼べる存在になっているが、曲終わりでは小松が前に駆け出してきて橋本が「世界を終わらせて」を歌う隣で全員が並んで体を揺らす。そうしてから戻って楽器を鳴らすことによってより込み上げてくるものが確かにある。なんだかみんなで肩を組んでこの曲を歌いたくなるような。それは時折メンバーがやることでもあるのだけれど。
そして橋本は
「眠れない夜を超えて ROCK IN JAPANに来たんだ」
と「アストロビスタ」を歌い始めると、曲中の最も極まる部分と言える
「忘れないでほしい」
のフレーズをを少し飛ばしてまでも、
「ROCK IN JAPAN、会いたかったぜー!」
と高らかに思いっきり叫ぶ。ああ、本当にそうだ。2019年の1回しか出演したことがないし、このフェスでおなじみと言える存在ではない。でもどのフェスよりも自分が大好きでずっと通ってきたこのフェスで会いたかった。こんなに大きなフェスの大きなステージでハルカミライのパンクが響く瞬間を目にしたかったんだ。それはこの日ついに現実になった。日本最大級のフェスのメインステージで、ハルカミライの音楽が確かに鳴っていた。メンバーもこのフェスを好きでいてくれていたらそんなに嬉しいことはないけれど、こんなライブができる場所なら絶対に好きに決まっている。
しかし体感的にもあまりにあっという間だったこともあり、須藤が時間を確認するとまだかなり時間があるということで、JAPAN JAMの時と同じようにここからは時間の許す限りに怒涛のショートチューンの連打となるのだが、その口火を切る「Tough to be a Hugh」を演奏しようとすると橋本はバンドを制して
「俺の歌から始める」
と言ってアカペラから歌い始めたあたり、本当に何にも決めていない、その場でその瞬間に全て決めているんだろうなということがわかる。それは毎日のようにライブをやっているバンドだからこそできる野生のカンのようなものだろう。
そうしてショートチューンを連発しまくって時間ピッタリになったかと思いきや須藤は
「でも前説2分押したからもう1曲やります!」
と言って、リハも含めたらこの日6回目となる「ファイト!!」で全てを出し尽くした。もう何回あいつはぶっ飛ばされたんだろうかと思うくらいに。
リハも含めたら余裕で20曲を超えていた。こんなライブは間違いなくハルカミライにしかできない。それはロッキンという場所であってもハルカミライが変わることはないということであるし、きっとこれから毎年このステージでこんなライブを見ることができる。ハルカミライのファンはもうハルカミライを見るためにこのフェスのチケットを取っても絶対後悔しないというか、そうすべきだなと思うくらいにこの日1発目にしてあまりにも凄まじくハルカミライらしいライブだった。
リハ.ファイト!!
リハ.エース
リハ.フュージョン
リハ.Tough to be a Hugh
リハ.To Bring BACK MEMORIES
リハ.ラブソング
リハ.ファイト!!
1.君にしか
2.カントリーロード
3.ファイト!!
4.俺達が呼んでいる
5.春のテーマ
6.ファイト!!
7.フュージョン
8.夏のまほろ
9.ウルトラマリン
10.PEAK'D YELLOW
11.世界を終わらせて
12.アストロビスタ
13.Tough to be a Hugh
14.フュージョン
15.ファイト!!
16.To Bring BACK MEMORIES
17.フルアイビール
18.ファイト!!
11:25〜 オレンジスパイニクラブ [HILLSIDE STAGE]
もともとはこの枠はなきごとが出演する予定だったのだが、メンバーのコロナ感染でキャンセルになったことによって、このオレンジスパイニクラブが急遽出演することになった。何なら代打じゃなくて普通に出演していても全くおかしくない存在だと自分は思っているバンドである。
メンバーがステージに登場すると、実に普通というか見た目の派手さは一切ないバンドなのであるが、ベースのゆっきーはどこか髪が長い時の菅田将暉のように見えるのが不思議であるし、ドラムのやはり髪が長いゆりとが黒のサングラスをかけているというのも少し意外である。
するといきなりの、SNSでバズってこのバンドの存在を知らしめた「キンモクセイ」という最大の代表曲を1曲目に演奏することによって歌詞のとおりに「あんた最高」と思わせてくれるのであるが、もしかしたら共感できるラブソング的に広がったかもしれない曲であるのだが、兄であるスズキユウスケのボーカルも、弟であり時にはツインボーカル的なパートも担うスズキナオト(ギター)のコーラスも声に甘さは全く感じられない。むしろその声はロックバンドをやるためにもたらされたかのような強い攻撃性を感じさせる。
だからこそその「キンモクセイ」のイメージをライブという場で覆すかのようにーというよりはかつては銀杏BOYZに影響を受けてドーテーズという名前で活動していたという個人的にラブソングよりもはるかに共感しまくりのエピソードを持つバンドであるだけにそうした面こそが本質であるかのように、「君のいる方へ」「スリーカウント」とスズキ兄弟の荒々しさすら感じる歌声ともはやパンク的と言えるようなバンドサウンドをぶっ放すように演奏していく。これは「キンモクセイ」が聴きたくて観にきたというような人でもイメージが変わらざるを得ないだろう。
しかしながらユウスケは本来このステージに立つはずだったなきごとへ拍手を送ったりするあたりからはダメ人間ではあれどクソ野郎ではないというこのスズキ兄弟をはじめとしたこのバンドのメンバーの人間性を感じさせてくれる。しきりに2日前に急遽出演が決まったということも口にしていたけれど。
リズミカルに体を揺らすような「タルパ」から、もうこの歌詞はこのくらいに振り切ったダメ人間でないと書くことはできないであろう、「キンモクセイ」のイメージだけで来た人は引いてしまうかもしれないくらいにどぎつい歌詞が並ぶ「モザイク」、さらには破壊的というか自己破滅的とすら言えるくらいのパンクサウンドの「急ショック死寸前」と、むしろこのバンドの本質の部分を見てくれと言っているかのようですらある。だからこそユウスケは
「ロッキンは憧れの一つ。急に出ることになったから実感があんまりないけど。
でも俺たちもツアーを廻ります。今日見て、なんか思ったよりも良いなとか、こんなバンドなんだって思ってくれたりしたあなたに来てほしいです」
と言ったのだろう。この曲たちをしっかり受け止めてくれるような人がたくさんいることをわかっているのだ。
そして最後に演奏されたのは、タイトル通りに銀杏BOYZの影響をモロに感じるような「敏感少女」。その演奏する姿を見ていて、自分の中でこのバンドのイメージがハッキリと変わった。「TikTokでバズって〜」みたいな形容詞は自分には縁遠く感じてしまうけれど、むしろこのバンドは自分のように銀杏BOYZに影響を受けてしまって、自分には音楽しかないと思ってしまうような奴のための音楽なんじゃないかと思った。だからユウスケの言葉の通りにツアーにも行きたいと思ったし、もし行ったらより一層自分のためのバンドだと思える気がする。
「また来年」
と最後にユウスケはボソッと口にしたけれど、その言葉が現実になって欲しいというか、なるべきバンドだと思った。まさかこんなにもカッコいいバンドだなんて。本当に「あんた最高」だった。
1.キンモクセイ
2.君のいる方へ
3.スリーカウント
4.タルパ
5.モザイク
6.急ショック死寸前
7.敏感少女
12:00〜 Hump Back [GRASS STAGE]
サウンドチェックからそのままステージに残って本番を迎えると林萌々子(ボーカル&ギター)は
「先に水飲んでおきや。これからライブ始まったらすぐに暑くなるから!」
と宣言する。JAPAN JAMでも2年連続で最高にカッコいい姿を見せてくれたこのステージにHump Backが帰ってきた。すでに日本武道館でもワンマンをソールドアウトさせているが、ついにロッキンでもメインステージへの登場である。
そんなこのバンドのストレートなロックサウンドを真っ直ぐに響かせる「LILLY」からスタートすると、やはり林のボーカルは空高くに突き抜けていき、ぴか(ベース)は本当にこのステージに立っていることが楽しくて仕方がないというように飛び跳ねまくりながら演奏しているのだが、いつもスウェットを着ていて暑くないのだろうか。顔にはやはり汗が滲んでいるが、それは白のロンTという出で立ちが変わらない美咲(ドラム)もそうである。
拳を振り上げるというよりも観客の体を心地良く揺らせてくれるようなサウンドの「恋をしよう」という曲をこの序盤で演奏するというあたりには大きなステージでのライブに慣れてきた余裕のようなものを感じさせるのであるが、林はここにいる全ての人=少年少女への想いを口にしながらも、
「1つだけロッキンに文句言っていい?HY見たかったー!」
と、自分たちのライブと被ってしまって見ることが出来なくなってしまったHYが青春のサウンドトラックの一つであることを口にする。JAPAN JAMでもモーニング娘。のライブを見て振り付けを踊っていただけに、硬派なロックンローラーというイメージもある林は実はかなり幅広い音楽の趣向を持っているようであるし、そうした音楽遍歴がこのバンドのメロディのキャッチーさに繋がっているんだろうなということが様々なスタイルや世代のアーティストが居並ぶフェスに出るのを見るとよくわかる。
すると林のボーカルとバンドのサウンドがさらに伸びやかに突き抜けていくことによって客席の少年少女たちも笑顔で拳を振り上げる「オレンジ」から、先程このステージに出演していたハルカミライにも通じるようなショートチューンの「宣誓」では林が自身のマイクスタンドをぶっ倒しながら歌い、その際にコードが絡まりまくってしまう。そのコードを直すスタッフを称えるというのもなんだか林らしい感じがする。
その林は前日に近くのホテルに泊まって前乗りしていたということを明かすと、
「ホテルの近くで夏祭りをやっていて、盆踊りが始まるっていうからベンチに座って待ってたら、隣に85歳のおばあちゃんが座ってきたから話してたら、今でも好きな演歌歌手のコンサートを見るのを楽しみに生きてるって言ってて。
それって私たちと一緒やん!って。何歳になっても好きなものがあるから生きていけるんやなって。だから私たちも明日ライブやってくるよって言って」
というおばあさんとのエピソードを話す。その話を聞いていて、自分は85歳になってもライブに行くことができているだろうかと思った。今のままならきっとそうなっているだろうけれど、その歳になっても音楽やライブが生きている理由になってくれていたら幸せだろうなと思う。好きなバンドがまだ活動してるっていうことでもあるのだから。
そんなMCから繋がるのは、そのおばあちゃんも含めて全ての少年少女への想いを込めて鳴らされた新曲「がらくた讃歌」。もうリリースが迫ってきているけれど、きっとこれからもこのバンドのライブを担っていくことになるであろうストレートなロックンロールである。
それは今に至るまでのこのバンドのライブ定番曲であり、「ティーンエイジ」というタイトルでありながらもここにいる全ての人に向けて歌われた「ティーンエイジサンセット」へと繋がっていく。それは歌い方や描き方は多岐に渡れど、このバンドが歌っていることはずっと変わらずにいるんじゃないかと思えてくる。
すでにMCをしたからか、普段は演奏前に林がギターを爪弾きながら思いを口にして演奏されることも多い「番狂わせ」は、ここまでに少年少女のための曲を歌ってきたからこそ、すでに大人になった自分のような年齢の人間が聴いても
「おもろい大人になりたいわ」「しょうもない大人になりたいわ」
と思うのであるし、それはメンバーもきっと同じ思いでこの曲を鳴らしているんじゃないかと思う。
だからこそこのフェスでのライブでも林のボーカルを軸にしたバラード曲「きれいなもの」の純真さがダイレクトに響いてくるし、こうした聴き入るようなタイプの曲を堂々と演奏できるのもまたこのバンドの強さであるが、その純真さはそのまま「拝啓、少年よ」へと繋がっていき、林が声を張り上げて
「空がキレイだぜ」
と歌う時に観客が腕を突き上げた真上に広がる空は雲がかかっていてもキレイに見えるというか、うっすら晴れ間が射していたのはこのバンドが招いたものなのだろうか。
そして
「みんなこの曲知らんだろうけど、知らんくても楽しめる曲やから!」
と言って演奏された、パンク的なサウンドの新曲の「僕らの時代」では時間がないのを察知したのか林が2人を
「急いで急いで!」
と急かして演奏したことによって、より曲のテンポが速くなってパンクさが強くなる。その時間との戦いもまた盟友であるハルカミライと通じるようなところがあるのだが、無事に最後まで演奏しきると安堵の表情を浮かべてステージから去っていった。その姿からはもはや貫禄にも似た頼もしさを感じるようになっていた。
林はよく歌詞を変えて歌ったり、曲中に思いを込めた言葉を口にしたりするが、ライブ後半には
「今年の夏はロッキンがあるから大丈夫!」
と口にしていた。それと同時にライブハウスでは毎日のようにこうしたライブが行われていることも。そうしてライブをすることによって守っていくという戦い方を選んだHump Backだからこそ、JAPAN JAMの2年を経てようやく夏にロッキンに出演することができた意味の大きさをわかっているはずだ。でもそれはこのステージが終着点ではなくて、これから先もずっと続いていく。そんなこのバンドがいてくれればずっと少年少女のままでいることができると思える。かつて初めてこのロッキンに来た時を思い出すかのように。
1.LILLY
2.恋をしよう
3.オレンジ
4.宣誓
5.がらくた讃歌
6.ティーンエイジサンセット
7.番狂わせ
8.きれいなもの
9.拝啓、少年よ
10.僕らの時代
12:45〜 フレデリック [LOTUS STAGE]
3年前にはひたちなかのGRASS STAGEにも立った、フレデリック。JAPAN JAMでもCOUNTDOWN JAPANでも「俺たちの」という形容詞を付けていただけに、3年振りとなるこのロッキンのステージにも並々ならぬ思いがあるはずである。
「ジャンキー」のリミックスのようなSEでメンバーがステージに現れると、髪に緑色が混ざっている割合が増えてきているように見える三原健司(ボーカル&ギター)が
「ロッキン、3年振りの開催おめでとうございます。3年振りのロッキンのフレデリック、40分1本勝負、よろしくお願いします!」
と自らに気合いを注入するかのように口にしてからいきなりの「KITAKU BEATS」で軽快かつコミカルな電子音的なサウンドを赤頭隆児(ギター)が奏で、三原康司(ベース)の音階的にも肉体的にもうねりまくるベースと高橋武のアタック感の強いドラムのリズムに合わせて観客は手拍子をして踊りまくる。
すると健司は早くもハンドマイクになって、歌詞に合わせて客席に手を振りながら
「よく来たね〜」
と声を掛けるのは「シンセンス」であるが、サビで思いっきり手数を増やすだけではなくて、高橋のドラムは間奏で激しいビートのアレンジを施しており、それがそのままこのライブならではのものとして響くと、それはやはり気合いに満ち溢れているからこそのものであることが伝わってくる。
それは歌詞の通りにみんな優勝するためのダンスアンセムである「オンリーワンダー」でもやはりビートの強さがそのままより踊れるサウンドとなって我々を踊らせてくれるのであるが、そんな中で演奏されたこの時期にピッタリ過ぎるくらいにピッタリな「熱帯夜」では健司が左右に手を振る姿に合わせて観客も同じように手を振る。
ライブ初披露だったJAPAN JAMではその手を振るタイミングがなかなか合わずに健司も苦笑いしていたのであるが、それからツアーの各地や代々木体育館というアリーナでも鳴らされたことによってこの曲はやはり大きく化けた曲になったし、健司は高音部分がキツそうに感じる時もあったが、ハンドマイクゆえにカメラに目線を合わせるというか、ステージ上でヤンキー座りのようにしてカメラを見つめて歌ったりと、ロックスターっぷりがまたも大きく向上している。だからこそこうして巨大なステージで見るのがしっくりくるというか。
そうしてここまでは今の最新のフレデリックを見せつけるような内容になっていたが、ここで健司はロッキンには2015年からずっと出演し続けていることの感謝を告げると、その初出演時に演奏していた「愛の迷惑」を実に久しぶりに演奏する。きっとファンはみんな聴きたい曲であるということをわかっているからこそ、こうしてここで演奏されることによってロッキンへの思いの強さを知ることができるし、まだ規模が拡大する前だったとはいえ、PARK STAGEを初出演にして満員にしてみせたあの時のライブはこのバンドがいずれメインステージに立つということを予期しているかのようであった。もちろん今鳴らされるこの曲はその強靭なビートと健司のボーカルとフロントマンとしての逞しさによって、今のフレデリックだからこその強さを感じさせるものになっている。
そして健司は
「ロッキン!音楽大好きっていう人はどれくらいいますか!両手を挙げてくれ!」
と言うと、その音楽が大好きであるという思いを自分たちの音楽にしてきた最新系の曲と言える、代々木体育館で新しいフレデリックの代表曲になった「ジャンキー」が演奏される。こうしてライブで聴くと、楽しくて仕方がない中にも感動がありすぎたあの代々木のライブを思い出してしまう。それくらいにこの曲はもうファンにとっては大事な曲になっているし、そんな曲がロッキンのメインステージで鳴らされているというのは本当に音楽が大好きで、こうしてこの場所にいることができて良かったなと思える瞬間である。
そんなライブの最後を担うのは康司のベースがうねりながらも疾走感を生み出し、それを高橋のドラムが加速させるというセッション的な演奏から突入していった、今やフェスシーン最大のアンセムとなった「オドループ」で、観客は腕を上げたりMVと同じ振り付けをしたりして本当に楽しそうに踊っているのであるが、「愛の迷惑」同様にこの曲も2015年の初出演時に演奏されていた。
でもあの時と決定的に違うのは、もう今のフレデリックはこの曲だけが突出したバンドではないということ。それに並んだり、超えるような曲を次々と生み出してきた。それでも、
「踊ってたい夜が大切なんです
とってもとってもとっても大切です」
というフレーズがより強い意味を持って響くようになってしまったこの数年間だったからこそ、こうした場所の大切さを確かめるようにこの曲を最後に鳴らす。そして健司はまた最後に観客に問いかける。
「音楽が大好きっていう人は両手を挙げてくれ!」
様々な出演者やフェスのTシャツを着た観客が全員両手を挙げている光景を見て、やっぱりこれがあれば大丈夫だと思った。それは音楽への愛をひたすら歌い続けてきてくれたフレデリックのライブだからこそそう思えたのだ。
1.KITAKU BEATS
2.シンセンス
3.オンリーワンダー
4.熱帯夜
5.愛の迷惑
6.ジャンキー
7.オドループ
13:30〜 KANA-BOON [GRASS STAGE]
ずっとGRASS STAGEに出てきたイメージも強いKANA-BOONであるが、実は初出演は他の若手バンドと同じようにWING TENTで、そこからLAKE STAGEを経てGRASS STAGEにたどり着き、そのステージを担ってきたバンドである。そんなバンドの3年振りのロッキンはバンドの新体制で初めてのロッキンにもなる。
なのだが実はフレデリックのライブの終盤から空を黒い雲が覆い始めて遠くの空では雷が光るという「大丈夫か?」という状況の中でのライブはいきなり古賀隼斗(ギター)があの軽快なギターを刻む「ないものねだり」からスタート。一時期よりかなりスリムになったようでいて、髪型がVaundyのようになっている谷口鮪(ボーカル&ギター)は早くも声が出せない我々に手拍子でリズムを任せて、ここにいる全員をKANA-BOONのドラマーにしてしまうのであるが、鮪はやはり痩せたことによって動きや挙動の一つ一つから歌唱に至るまでが実にシャープになったように感じる。それは鮪が健康的な生活を送れている証拠でもあるだけにどこかホッとするのだ。
そんな中で「Torch of Liberty」とアッパーな曲が続くのであるが、KANA-BOONのメンバーとして初めてこのロッキンのステージに立つマーシーこと遠藤昌巳(ベース)がグルーヴィなベースプレイだけではなくて体全体を使って観客を煽るような仕草を見せているというのはこれまでのKANA-BOONのライブにはなかった要素と言える。
だからこそ最新アルバム収録の、
「このステージこそが俺の居場所!」
と言って演奏されたダンスチューンの「マイステージ」も実に肉体的というか、ここにきてロックバンドの持つ衝動のダイナミズムを存分に感じさせるようになっている。
とはいえMCでは小泉貴裕(ドラム)の胸ポケットに猫の刺繍がされていたり、対照的に鮪は犬が3匹ほどプリントされているTシャツを着て可愛さをアピールしたりという緩さは変わらないのであるが、演奏になると「フルドライブ」から文字通りに猛加速していく。曲のBPM自体は変わっていないはずなのであるが、過去最高に速さを感じるように思えるのは今のバンドの状態がエネルギッシュ極まりないということであろう。
そのまま問答無用の名曲「シルエット」へと突入していくという代表曲にして名曲の連打に次ぐ連打は休むこともステージを離れることも許さないし、改めてKANA-BOONがフェスという場で本当に強いバンドだなということを感じさせてくれるのであるが、こうして曲を演奏しているうちに雷が鳴っていたほどの分厚い雲が過ぎ去り、なんと晴れ間すら見えてくるという状態に。JAPAN JAMではめちゃくちゃ雨が降っていただけにやはり雨バンドであることを自認していたが、こうして雲を吹き飛ばしたということは今のKANA-BOONが太陽が似合うくらいに眩しい力を放っているバンドだからと言えるのかもしれない。実際に鮪は
「俺たちが太陽を連れてきたから!」
と自信満々に口にしていた。
その自信があるのも頷けるくらいにバンドのアンサンブルが極まり、古賀のシャープなギターも小泉のパワードラムも、遠藤のうねるベースも、何よりも鮪の力強いボーカルの伸びが、今のKANA-BOONは実は過去最強の状態にいるんじゃないのかと思わせるのが「まっさら」であり、何よりも鮪は本当に歌が上手い。こんなに歌えるボーカリストがまた歌い続けることを選択してくれて本当に良かったなと思うくらいに。
そんな中で鮪は新曲を演奏することを告げる。その新曲「きらきらり」はNARUTOの続編であるBORUTOの主題歌であり、つまりは「シルエット」の続編と言えるような曲。だからこそタイトルからも感じられるようにメロディが煌めいているのであるし、鮪が大好きな漫画であるだけに一世一代の名曲を生み出そうという意識が曲に確かに宿っているし、きっと「シルエット」のように漫画を読むとより深く理解できるであろう歌詞も散りばめているのがKANA-BOONなりのタイアップへの向き合い方であるだけに、NARUTOとBORUTOを一気に読んでみたいなと思う。それは果てしなく長い道のりだけれど。
そうしているうちになんやかんやで暑さすら感じるくらいに晴れてきており、そんな空模様と3年振りのこのフェスの開催を祝うようにして演奏されたのは、この日この後に出演するフジファブリックの金澤ダイスケとともに作り上げた「スターマーカー」で、サビではやはり煌めくようなサウンドに合わせて観客が腕を左右に振る。遠藤がステップを踏むようにベースを弾いているのも実に素敵である。そうして今の編成になって初めてのロッキンで、今のKANA-BOONがロックバンドとして生きている衝動を全放出するようなバンドになった。この日のライブはそれを確かに示すものだった。
しかし自分は鮪が休養した時に、もう毎回フェスに出たりしなくていいから、自分のやりたいことだけをやっていて欲しいと思っていた。今となればそんな自分が思っていた以上に鮪は強い人間だったんだなと思わざるを得ないが、こうして今も最前線に立ち続けることを選んだからこそ、今こんなにも強くて逞しいKANA-BOONの姿を見ることができている。
鮪は最後に先ほどライブを終えたフレデリックと2マンライブを行うことを告知したが、そうしてライブ猛者たちと2マンツアーを回るということができるのも、KANA-BOONがこうした場所に戻ってくることを選んだからだ。なんだか、WING TENTで初出演した時の「凄いバンドが出てきたな」って思った時よりも今の方がKANA-BOONというバンドにドキドキしているし、これからもっと凄いものを見せてくれる予感がしている。そう思えるのがこの上なく嬉しいのだ。
1.ないものねだり
2.Torch of Liberty
3.マイステージ
4.フルドライブ
5.シルエット
6.まっさら
7.きらりらり
8.スターマーカー
14:45〜 ビッケブランカ [PARK STAGE]
実はライブが始まる時間を間違えてしまっており、青空が広がってきて暑くなってきたことで呑気にビールを飲んだりしている間にすでにビッケブランカのライブは始まってしまっていた。
バンドメンバーとともに演奏しているビッケブランカは装飾が施された自身のピアノをサングラスをかけた状態で歌っており、そこからさぁステージ前に出てきてハンドマイクで歌う…というところでサングラスを外そうとするのだが、その瞬間に太陽の光が眩しくて目がやられそうになるという小芝居も挟まれるというあたりのエンタメっぷりはさすがである。
そうしてサングラスを取ってハンドマイクで歌う「This Kiss」のサビではビッケブランカの仕草に合わせて観客の腕が左右に揺れるのであるが、元来ピアノマンである彼がこうして歌に専念できるのは井手上誠(ギター。前日は秋山黄色のメンバーとして出演)らバンドメンバーの存在によるところが大きいのだろうし、キーボードのメンバーに委ねることで自身の歌唱に専念して曲のキャッチーさを最大限に伝えようとしている。
そんなビッケブランカはステージから距離が離れている、客席の丘の上で寝転がったりしている観客に向かって
「君たちも僕のことを見てるの?(笑)
(手を振る観客を見て)あ、見てくれてるのね(笑)ありがとう。
ロッキンは初めて僕がフェスに参加した思い入れの強いフェスです。そこにこうして戻って来れて本当に嬉しいです。でもライブの楽しみ方みたいなものが変わったりしたけれど、今こうしてこのステージに立つことによってみんなの熱量を感じていると、もう元通りだなって思う。それくらいに感じられるものがあります。本当にありがとう」
という真摯極まりないMCにはそれこそステージから距離がある丘の上に寝ている人も含めて大きな拍手を送っていた。ビッケブランカがそう思えたということは、我々がステージへ向ける熱量が声を出せたりしなくても声を出せた頃と同じくらいに伝わっていたということだ。なんだかそれが本当に嬉しかったのである。
するとシュールかつファンキーな「Ca Va?」で観客もバンドメンバーも踊りまくり、ビッケブランカも飛び跳ねたりしながら歌うのであるが、その跳躍力の高さはこの男が意外に運動能力が高いんじゃないかと思わせるし、この曲は聞くと本当に耳から抜けないくらいに癖になる。かといって鯖を食べたくなるかと言われるとそうは思わないけれど。
そして最後はビッケブランカのポップさの極みとも言えるような、野外に実によく似合う「ウララ」が演奏されて、やはり観客はサビで腕を左右に振るのであるが、間奏ではビッケブランカとバンドメンバーたちがあらゆる方向から見ている観客に向かって実に丁寧に手を振る。(井手上がドラムのライザーの上に座り込んでいるのも実に面白い)
そうした挙動やMC、歌声や曲からもビッケブランカの人間性が伝わってくるというか、本当に良い人なんだろうなと思える。それが真っ直ぐに伝わってくるようなライブをビッケブランカはやっている。それは決して激しく魂を燃やしまくるというタイプではなくても、彼がライブアーティストであるということの証明なのかもしれない。
1.Moon Ride
2.アシカダンス
3.This Kiss
4.Ca Va?
5.ウララ
15:45〜 THE BAWDIES [LOTUS STAGE]
元々はこの枠はBiSHが出演する予定だったのが、アイナ・ジ・エンドがコロナに感染したことによって無念の出演キャンセルとなり、代わりに急遽出演が決まったのが代打屋・THE BAWDIESである。ちなみにバンドはかつてもgo!go!vanillasがライブが出来なくなった時にバニラズが抑えていた下北沢SHELTERで代わりにワンマンライブをやるという代打ホームランをかっ飛ばした経験がある。つまりはバンド界の代打の神様・八木裕的な存在である。
「何分急なもんで、ちょっと音を出させてください!」
とROY(ボーカル&ベース)が言ってのサウンドチェックではメンバーは全員ジャケットを着ていなかったというのはあまりに暑かったからかもしれないが、本番ではしっかりスーツを着て出てくるというのがTHE BAWDIESというバンドのスタイルであるのだが、この日はやはりいつもとは違うというのは演奏を始める前にROYは
「アイナさん、BiSHのメンバーやBiSHを楽しみにしていた人たちが少しでも笑顔になれますように!」
と口にしてから爆音ロックンロール「IT'S TOO LATE」を鳴らし始めた。THE BAWDIESがやることは普段と全く変わらない。自分たちのロックンロールをやるということ。だからカバーをしたり、特別な演出を使うというようなこともない。でもこの日は間違いなく普段の自分たちだけではない思いを音に乗せて届けようとしていた。
曲終わりのROYの超ロングシャウトに反応して拍手が起こったりと観客が少しずつ増えてきているのも嬉しいけれど、
「今日は盛大なお祭りだと聞いております!打ち上げ花火の用意はいいですか!皆さんが打ち上げ花火になるんですよ!」
という言葉の後に演奏された、ロッキンでも数え切れないくらいに聴いてきた「YOU GOTTA DANCE」で飛び跳ねまくっていると、本当に今年もロッキンでTHE BAWDIESのライブが見れているという感覚にさせてくれるし、前方エリアで自分の前にいた人がTHE BAWDIESのTシャツを着ていた(タオルはTHE KEBABSだったので自分と同じような音楽が好きだと思われる)のは、急遽決まったとしてもTHE BAWDIESのライブが見れるのが嬉しくてTシャツを着てきたんだろうなと思う。
すでに汗を飛び散らせながらステージを激しく動き回ってギターを弾くJIM、一方でバンドの重要なリフを担うTAXMAN、1人だけジャケットを早くも脱いでシャツ姿になっているMARCY(ドラム)の3人が声を出せない我々の代わりにコーラスを思いっきり歌ってくれているようにすら感じられる「LET'S GO BACK」、歌詞に合わせて指を動かすという仕草を前方エリアの人がやっているのが、ちゃんと曲を知っていて普段からTHE BAWDIESのライブを見ている人がこの日にいるんだなと思えて嬉しい、ブレイクを経ての曲後半で一気にロックンロールサウンドが爆発する「SKIPPIN' STONES」と続くと、
「新曲をやりたいと思います!知らない人からしたら全曲新曲だと思いますけど、我々EPを出して先日までツアーを回っていまして。新曲中の新曲です!(笑)」
というROYのMCもアウェーな場ではあっても割とウケていたような感覚があっただけに、面白い人たちだなというのが伝わってくれていたら嬉しいのであるが、その新曲「STAND!」はガレージロックに振り切った今年リリースの新作EP収録曲。その衝動を炸裂させるような荒々しいサウンドと、アウェーの場をひっくり返そうとするような勢いが、ロッキンに何度も出演してきた、もはやベテランと言える立ち位置であるこのバンドをまるで初出演している若手バンドであるかのように感じさせてくれる。
という雰囲気を一変させるのが、
「初めての方が多いと思うので、先に説明しておきますね。我々はこれから「HOT DOG」という曲の準備に入りますので、しばしお待ちください!」
と言ってメンバーが楽器を置いて始まったこの日の「HOT DOG」劇場は卓子(TAXMAN)とソウダセイジ(ROY)の出会い編という、おそらく1番やってきた回数が多いもの。それはこれが初めて見る人にも1番わかりやすいというのもありつつ、著作権的な問題に触れないネタであるというのもあったんじゃないかと思う。
そんな「HOT DOG」で客席もさらに飛び跳ねまくっている姿を見ると、やはりこの曲は知っているという人も多かったんじゃないかと思う。
そのままお祭り騒ぎなので「T.Y.I.A.」とアッパーなロックンロールを連発するのだが、この曲のコーラスをロッキンでメンバーと一緒に歌いたかったなというのは今回の出演最大の悔いだ。それはどうしようもないことであるし、メンバーが演奏している姿を見て、音を聴くだけでも最高に楽しいのだけれど。
そんなお祭りは楽しすぎるがゆえにあっという間に終わってしまう。MARCYがリズムをキープしながらTAXMANのリフが鳴り響くのはかつてPARK STAGEのトリを務めた時(2010年だったか)にはリリース前の新曲として演奏されていた「JUST BE COOL」。そう考えるとロッキンでのこのバンドの歴史も長いものになったなと思うのだけれども、満員とはいかないまでも多くの観客が飛び跳ねまくる姿がステージから客席を映すカメラによってスクリーンに映るのを見て、確かに伝わるものがあったんじゃないかと思ったし、JIMがいつものようにマイクを通さないで
「ありがとうー!」
と何度も叫ぶ姿を見ていて、その言葉をこっちがバンドに叫んであげたかったと思った。それが出来ないから、今言う。出てくれて本当にありがとう。ROYは最近おなじみの、ステージから去ろうとして立ち止まってポーズを取るというパフォーマンスをして笑いを生み出していたけれど。
代打での出演が決まった時、嬉しかったけれど「もう普通には呼ばれなくなってしまったんだな」と思った。それでもわかっていたことでもある。毎回ワンマンに行っているから、規模が小さくなってきていることも。
でもそんな状況でのライブだったからこそ、かつて初出演のSEASIDE STAGEからPARK STAGE、LAKE STAGEと各ステージのトリを駆け上がり(PARK STAGEでのライブはロッキンに通い続けて見てきた中で5本の指に入るくらいの素晴らしいライブだった)、GRASS STAGEまで辿り着いた。それはTHE BAWDIESがアウェーをホームに変えてきた歴史そのものだった。その頃にライブを見ていた感覚を思い出すことができたライブだった。
ヒーローは遅れてやって来るというのなら、この日のTHE BAWDIESは自分にとってのヒーローだった。
リハ.A NEW DAY IS COMIN'
リハ.I'M IN LOVE WITH YOU
1.IT'S TOO LATE
2.YOU GOTTA DANCE
3.LET'S GO BACK
4.SKIPPIN' STONES
5.STAND!
6.HOT DOG
7.T.Y.I.A.
8.JUST BE COOL
16:45〜 フジファブリック [HILLSIDE STAGE]
2000年代前半、つまりはロッキンの勃興期からどんなことが起こってもこのフェスのステージに立ち続け、昨年のJAPAN JAMでもこのフェスへの思いを口にしていた、ロッキンを担い続けてきたバンドであるフジファブリック。今年は会場も変わったことでHILLSIDE STAGEへの出演。
前日には宮本浩次のバンドメンバーとして出演していた玉田豊夢をサポートドラマーに加えてメンバーが登場すると、日差し対策によってか金澤ダイスケ(キーボード)はサングラスをかけている中で、その金澤のキーボードと山内総一郎(ボーカル&ギター)の歌唱のみという形で「手紙」を歌いあげる。
このステージのキャパを超えるくらいの観客も全員がただただその歌唱にじっと聴き入ることで感じる静寂にも似た空気。それは場所が変わっても、何度もステージに立った「ロッキン」のライブだからこそ、空の上からこのライブを見ているであろう男に誰もが思いを馳せているかのようだった。
それは山内がこのフェスだからこそ叫ぶ
「ジャパーン!」
という言葉もそうだ。それは志村正彦がこのフェスのステージで何度となく叫んできたことでもあるし、志村のそれは彼の師である奥田民生から受け継いだものだ。今はそれを山内が背負っている。それはつまりこのフェスにおける歴史の一部を担っているということであり、それを背負った男としての強さが歌唱や立ち振る舞いにも確かに表れている。
基本的に演奏される曲は近年のフェスでのライブと変わらないので「SUPER!!」での加藤慎一(ベース)と山内がネックを左右に振り、それに合わせて観客も手を左右に振るという一体感も、妖しげなサウンドが歌謡性を感じさせるからこそ山内のボーカルが常に進化を果たしていることを感じさせる「楽園」も見慣れているものであるのだが、それでもやはり「ロッキンでのフジファブリックのライブ」はどんなにやる曲が同じでもやはり感じるものが違うのだ。
それは「夏の曲」と言って演奏された「若者のすべて」が最も顕著だ。ちょうどこの時間は夕方5時。チャイムのようにイントロで金澤のキーボードが鳴る。ロッキンで聴くこの曲はLAKE STAGEにずっと立ってきた志村のことや、その志村が居なくなってしまってからもあのステージに立ち続けてきたこのバンドのことを、何年経っても思い出してしまう。
でも、思い出してしまうのは忘れていないから。きっとこれからも毎年出演するであろうロッキンでのフジファブリックのライブでこの曲を聴けば、志村がこの曲を歌っていた姿や表情を思い出すことができる。きっとそういう思いを持った人がたくさんいるということをメンバーもわかっているはずだ。
でもそうした思いは決して後ろ向きな、ずっと引きずっているというものではない。フジファブリックは自分たちの活動によって前に進み続けることの意味を示してきたバンドだ。だから山内は
「僕らが皆さんの居場所になります!」
と宣言し、ここにいる人のこれからの未来に光が射しますようにという願いを込めて「光あれ」を演奏するのだ。ハンドマイクで歌う山内が手を振る仕草に合わせて観客も手を振るという光景がこの上なく美しいのはもちろんのこと、山内はステージサイドのカメラに寄っていってカメラ目線を向けて笑顔で歌う。こんなに強い姿を見せられたら我々が前を向かないわけにはいかない。最後に山内が再び
「ジャパーン!」
と叫んだのを見て、本当に強い人間たちによる強いバンドだなと思った。
志村が歌っていたライブも、山内が歌うようになってからのライブも、とりわけ3人でLAKE STAGEのトリを務めた時に山内が最後に
「忘れて欲しくないメンバーがいます。志村正彦!」
と紹介した時も。忘れることができない名場面をこのフェスで作ってきたフジファブリックのロッキンの物語はひたちなかから蘇我に場所が変わっても続いていく。その姿に我々が力を貰い続けている限り。今年のこのライブだって、これから何年経っても思い出してしまうんだろうな。
リハ.夜明けのBEAT
1.手紙
2.SUPER!!
3.楽園
4.若者のすべて
5.光あれ
17:25〜 My Hair is Bad [LOTUS STAGE]
アリーナツアーを敢行した今年はMy Hair is Badにとって大きな変化をもたらした1年になった。ミュージックステーションやサブスクの解禁という新たな挑戦。それが結果的にたくさんの人に届いてたくさんの人に求められるようになったことを示すように、空が青から薄らと色を変えてきているLOTUS STAGEの客席は満員である。
メンバーが出てきてのサウンドチェックで「優しさの行方」を演奏して、集まった観客を唸らせると3人は捌けることなくそのままステージ上で開演時間を待ってから本番へ。
するとこの日は珍しく椎木知仁(ボーカル&ギター)がギターを弾きながら
「はじめまして。My Hair is Badです。俺は新潟県上越市に生まれ、夏は野球のボールを追いかけて冬は雪が積もるような街で…」
と自身の生い立ちを語るというスタート。この語り自体はおなじみであるが、そこから始めるというのは実に珍しいし、それはこの語りをライブ途中に挟むことがない内容になるということでもあると言える。
なので椎木はその語りから繋がるようにして「ドラマみたいだ」を歌い始めると、ステージ前に出てきてギターを鳴らすのであるが、
「ロッキン、ドキドキしようぜ!」
と言ってから演奏されたおなじみの「アフターアワー」と続くと、椎木のギターも山本大樹のベースも山田淳のドラムもこの日最大級の爆音でこちらに届いてくる。3人の音しか鳴っていないシンプルなスリーピースサウンドだからこそそのサウンドはよりダイレクトにこちらに届いてくるし、それをこんなにも衝動的に届けてくれるのだから拳を振り上げざるを得ない。それくらいに今のマイヘアのライブはこれまでを更新する熱さに満ちている。
そんなマイヘアの持つメロディの美しさと、ラブソングでありながらもそこら辺の凡庸なラブソングのものとは全くレベルが違う物語を描く椎木の作家性が炸裂している「グッバイ・マイマリー」から、
「今はもう何も考えずにこの曲を歌える」
と言って歌い始めたのは「ブラジャーのホックを外す歌」としてミュージックステーション出演時に広まった「真赤」。当然ながらステージは真赤な照明に染まる中で椎木はギターを掻き鳴らし、山田はシンバルをぶっ叩く。ただインパクトの強い歌詞を歌うバンドではないロックバンドのカッコよさがこのバンドのライブからは確かに感じられる。
そのままこの日の最速を更新するかのようなショートチューン「クリサンセマム」で山本がステージ前に出てきてポーズを決めるようにしてからベースを鳴らすと、一気にサウンドがハードかつラウドになっていく「ディアウェンディ」では椎木は
「今が最高、最新、1番カッコいいMy Hair is Badだ!」
と目元でダブルピースを作りながら叫ぶと、
「このステージの名前の「LOTUS」の意味知ってる?ギリシャ神話に出てくる禁断の果実なんだって!一度食べたら止まらなくなるような。それって音楽そのものじゃないか!
マリファナでもコカインでもLSDでもMDMAでもない、これが音楽っていう最高なドラッグだ!」
と淀みなく次々と言葉を放ち、その言葉がバンドの演奏をさらに加速させていく。個人的にはこの曲での山本が笑顔でポーズを決めるのも椎木の言葉に並ぶ見どころの一つだと思っている。
そんな禁断の果実が実るこのステージの激しさと暑さを更新するような曲から一転して、椎木は穏やかにギターを爪弾くようにして「味方」を歌い始める。これまでもフェスでも「いつか結婚しても」などの壮大なメロディを持った曲を演奏してきたバンドであるが、
「きっとこれからも僕は正義にも悪にもなれないけど
誰よりも君の味方だ」
「君が笑えば なにもいらない
君がいれば 僕は負けない」
というフレーズはこうしてこのバンドを前にしている人の誰もが歌って欲しい言葉であり、そんな人がいるからこそバンドが歌える歌詞だ。山本のアウトロでのコーラスを含めて、こうした曲にこそこのバンドの優しさを感じられると思うし、そうした面も、素直な面も激情的な面もステージで隠すことなく見せてくれるこのバンドのメンバーたちは本当に人間らしいと思う。
そんな曲の後に椎木は
「今1番歌いたい曲。この曲を歌いに来たと言っても過言ではない」
とまで言い切ってから最新アルバム「angels」収録の「歓声をさがして」を演奏する。音楽を見失いそうになる数年間だったけれど、この曲は一つの出口を示してくれているし、だからこそこの曲を歌い鳴らすメンバーの表情は実に穏やかだ。「フロムナウオン」を演奏しないのもそういう理由だろうし、それはJAPAN JAMでも演奏していかなかっただけにこの場所はマイヘアをそうした心境にしてくれる場所なのかもしれない。そんな場所が来年には探すことをしなくても歓声が響いている場所だったらいいなと思う。
そんなライブの最後に演奏されたのは「夏の曲」と言って演奏された「夏が過ぎてく」。それはこの季節じゃないと聴けない、マイヘアの真髄のような曲。このライブがあっという間に過ぎ去ってしまったように、今年の夏も音楽を求めていろんな場所に足を運んでいる間にあっという間に過ぎていくんだろうなと思いながらステージから目線を上に上げるとまだ明るい。もう18時を過ぎているというのに、こんな時間になってもまだ明るいだなんて。
今でもこのフェスのWING TENTにマイヘアが初めて出演した時のことをよく覚えている。ずっとロッキンオンジャパンを読んでいたから憧れのフェスだったことを語りながら、椎木は
「1番デカいステージまで行ったら、ステージを飛び降りて客席に突入する」
と言っていた。実際にひたちなかでも1番デカいステージであるGRASS STAGEに立ったのだが、その時に椎木は客席に突入することをしなかった。そうしなくて本当に良かったなと思うのは、このフェスのルールを守り続けてきてくれたことで、我々は3年も期間が空いても、場所が変わってもこうしてこのフェスでマイヘアのライブを見ることができているからだ。
リハ.優しさの行方
リハ.カモフラージュ
1.ドラマみたいだ
2.アフターアワー
3.グッバイ・マイマリー
4.真赤
5.クリサンセマム
6.ディアウェンディ
7.味方
8.歓声をさがして
9.夏が過ぎてく
18:05〜 PEOPLE 1 [HILLSIDE STAGE]
まだライブ経験3回目にして今年の春にJAPAN JAMに出演し、そこで鮮烈なフェスデビューを果たした、PEOPLE 1。その際に渋谷陽一も
「このバンドの出演を発表した時にたくさんの人が喜びのコメントを書いてくれた」
と言っていたが、そのライブがこうしてまた夏にこの会場に戻ってくることに繋がったのである。
サポートのギター、ベースを加えた5人編成で、向かって下手側から帽子を被った姿が何度見てもハマ・オカモトに似ていると思ってしまうDeu(ボーカル&ギター&ベース)、見た目からして逞しさを増したように見えるIto(ボーカル&ギター)、キッズのような出で立ちのTakeuchi(ドラム)が前列に並ぶと、Itoが飛び跳ねるようにしてキャッチーなメロディを歌う「魔法の歌」からスタートするのであるが、JAMの時のライブ開始時の緊張感はどこへやらというくらいにこの日はもう最初から堂々としているというか、もう楽しみきってやる!というメンバーの思いがその姿に溢れ出ている。
Deuがハンドマイクでメインボーカルを担う「怪獣」「スクール!!」という曲においても、JAMからの3ヶ月でこのバンドに何があったんだろうかと思うくらいに、このバンドは急にライブバンドとして化けたなということが瞬時にわかる。元からファンキーな曲であるのだが、JAMの時はまだどんなもんかと大人しく見ていた感も強かった観客もこの日は踊るしかないだろ!とばかりに踊りまくっている。それはサポートメンバーたちもガンガン前に出てきて演奏したり、ItoとDeuもステージ上で暴れまくっているかのように激しく動きながら歌っているというステージ上の熱量が観客側に伝わっているからであり、もうこの時点で楽しさがJAMの時とは段違いだ。
それはこのバンドがJAM以降も対バンを含めてライブを重ねてくるという日々を送ってきたからであり、実際にJAMの時には新曲として演奏されていた「銃の部品」の華やかさすら感じるポップサウンドが完全にライブに欠かせないものとして馴染んでいる。何よりもItoが激しい動きを見せるだけではなく、その挙動がしっかりと歌に籠るようになっている。全然知らない人がこのライブを見たら、まだ数えられるくらいしかライブ経験がないバンドとは全く思わないだろう。
すると一転してDeuが椅子に座ってムーディーな空気感になる中で
「僕はこの日ここで歌うためにこの曲を作ったのかもしれない」
と言って「113号室」を歌い始めるのだが、シンセベースのリズムとサウンドを生かしたこうした激しさとは対極と言えるような曲の表現力もこのバンドは見事に獲得している。
そしてJAMの時に「この曲はこれからロッキンオンのフェスのアンセムになっていくかもしれない」と思わされた「常夜燈」が暗くなったこの会場に灯りを灯すかのような暖かさを持って鳴らされる。ああ、やっぱりこの曲はそうした存在になっていくんだろうなと改めて思ったのは、またJAMの時のようなデカい規模のステージでこの曲を聴きたいと思ったからだ。まだJAMの時は「さすがにステージがデカすぎるな」と思ったのだが、むしろ今はあの規模の方が似合うんじゃないかと思うほど。
それを証明するかのようにItoとDeuのツインボーカル的な歌唱による「エッジワース・カイパーベルト」はもはやステージ上も客席も祭りのピークであるかのような凄まじい盛り上がりっぷりを見せる。きっと各地のライブハウスで見てきた景色がこの曲をここまでライブ映えするものに育て上げたんだろうなと思うし、何よりもメンバー全員が本当に楽しそうに音を鳴らしている。経験が乏しいからライブが怖いなんて全く思ってないどころか、もっともっとこうしてライブをやりたい、そして目の前にいてくれている人と繋がりたいという思いが音からも姿からも溢れ出ている。だからこそ熱狂の中にも感動にも似た感情が芽生えているのを確かに感じていた。
全くMCを挟まないというのもひたすらに曲を演奏しまくりたいという思いからであろうけれど、そんなライブの最後に演奏されたのはファンを大衆と称するこのバンドによる「大衆音楽」。それはつまりこのバンドはやはり誰よりも今目の前にいる人に向けて音を鳴らしているということだ。Takeuchiの強靭すぎるビートによって狂乱的なサウンドの楽しさに包まれながら、もう完全にこのバンドのポップソングに夢中だと思った。何ならこの日の裏ベストアクトと言っていいくらいに超絶進化を遂げたことをわずか3ヶ月ぶりのライブでPEOPLE 1は証明していた。
たまにツイッターで「このバンドのライブを見て欲しい」と言われることがある。JAPAN JAMの時も今回も「PEOPLE 1を是非見て欲しい」という声をよくいただいた。そう言ってくれた人たちはこのバンドのライブの凄まじさをもう知っていたからこそ、自分にそう言ってくれたのだと思うけれど、もうそう言われなくてもこのバンドのライブをすぐに観に行きたい。それくらい、本当にこのバンドの大衆音楽に夢中になってしまっている。
1.魔法の歌
2.怪獣
3.スクール!!
4.銃の部品
5.113号室
6.常夜燈
7.エッジワース・カイパーベルト
8.大衆音楽
18:45〜 THE KEBABS [PARK STAGE]
普段からこのブログやツイッターを見てくれている人がもしいるのであれば、自分が佐々木亮介というa flood of circleのボーカリストのことが大好きで仕方がないことは理解していただけていると思う。そんな佐々木亮介がUNISON SQUARE GARDENの田淵智也(ベース)らと組んでいるバンドがこのTHE KEBABSである。
なのだが、大好きだからこそ、リハでステージに現れて
「俺もあいみょん観たかった〜」
と言っている亮介の姿を見て驚いた。派手なパジャマ姿であるのはフラッドの革ジャンとは違うTHE KEBABSの時の衣装であるのはわかっているのだが、髪色が金から緑色混じりになっていたからだ。ここにきての亮介のこの自由っぷりには自分もまだまだそういうやりたいと思ったことを自由にやっていいんだなと思わせてくれる。ちなみに田淵は
「俺もあいみょん見たかったけど、PEOPLE 1見れて嬉しかった〜」
とさすがの若手チェックっぷり。それがユニゾンが対バンイベントを主催する時にまだあまり知られていない若手バンドを呼ぶというラインナップに繋がっているのかもしれない。
そんな田淵はサウンドチェック時はサングラスをかけたりしていたのだが、本番ではいつも通りに外してライブに臨み、おなじみの「THE KEBABSのテーマ」で新井弘毅(ギター)がリフを刻み、鈴木浩介(ドラム)が激しいビートを刻む。このドシンプルなTHE KEBABSのロックンロールが初めてロッキンで、この蘇我の地で響き渡り、亮介はサビで高く飛び跳ねると同じように観客も飛び跳ねまくる。難しいことを全く考える必要のないTHE KEBABSのロックンロールはこうして頭を空っぽにして楽しむことができる。
鈴木と田淵のリズムが一気に加速する「恐竜あらわる」、おそらくはアニメ化が決定している某人気漫画から着想を得たと思われる、新井のギターのシャープさが炸裂する「チェンソーだ!」とタイトルを並べると実にアホっぽいけれど、その発想をダイレクトに音や曲にするというのもまたTHE KEBABSなりのロックンロールだと言えるだろう。
だし、何よりもTHE KEBABSはメロディが良い。それはa flood of circleとUNISON SQUARE GARDENのソングライターが曲を作っているのだから当然と言えば当然であるが、
「ロバート・デ・ニーロの袖のボタン」
という、何でこんな歌詞のサビ?と思うようなフレーズをこんなにもキャッチーかつロックンロールに昇華できるミュージシャンは他にいないだろう。亮介は右腕を高く掲げてそのロックンロールを歌うために持って生まれた声を高らかにこの蘇我の夜空に響かせる。近年の亮介はどれだけ酒を飲んでも素晴らしい歌唱を聞かせてくれている。
そんな亮介がギターを持つと、ここまでのストレートなロックンロールサウンドから聞かせるタイプのバラードと言っていいサウンドになるのは、サビでは田淵が普通に上手いボーカルを聞かせる「ラビュラ」なのだが、これまでにこの曲を聴いてきたライブでは
「今年の夏は海に行けなかったし
山にも行けなかったし
お祭り そもそもなかったし」
というフレーズがコロナ禍での夏を過ごさざるを得なかった、フェスというお祭りすらもなかった夏のテーマ曲として響き、その切なさに涙せざるを得なかったのが、この日は亮介は最後に
「今年の夏は海に行こうぜ 山にも行こうぜ!」
と叫んだ。それはこうしてお祭りが戻ってきた今年の夏だからこそ加えることができたもので、今までこの曲を聴いてきた時とは違った意味で涙が出てきてしまった。そのお祭りをこのバンドたちと過ごせているのだから。
すると「THE KEBABSは忙しい」から再びロックンロールサウンドに転じ、新井も荒ぶりながらギターを弾き、その横に田淵が立ったかと思えば亮介は新井の両足の間から頭を出している。この自由っぷりこそTHE KEBABSのライブの楽しさであるが、新井はSerial TV dramaで、鈴木はART-SCHOOLで何度もひたちなかのロッキンのステージに立ってきた。そんな2人が年月を経て亮介と田淵と一緒にロッキンのステージに帰ってきたのだ。それは亮介と田淵がこのバンドを始める時に望んだことの一つなのかもしれない。喋ることはなかった2人はこの景色をどう見ていたのだろうか。
そんな4人のライブはクライマックスへ。亮介も田淵もリズムに合わせて飛び跳ねまくりながら、亮介は腕を掲げて伸びやかなボーカルを響かせる「ジャキジャキハート」がやっぱりこのバンドの曲は最高にキャッチーだなと思わせながら、ここからまたどこまでも遠くまで行けると思わせるような力を我々にもたらしてくれる。
それでもまだライブは終わることはなく、亮介は
「ROCK IN JAPANに何しに来たの!?ロックンロールでしょ!」
と思いっきり叫んでから、再び「THE KEBABSのテーマ」を演奏するのだが、最初とは全く歌詞が違っていて、鈴木にやたらと絡みながら歌うというバージョンになっていた。そうした自由さを含めて、THE KEBABSは、亮介はロッキンの「ROCK」の部分を自分たちが担って守っていこうとしている。その姿勢こそが何よりもロックンロールなのだ。あまりにも会心過ぎたPARK STAGEのトリのTHE KEBABSのライブ。もはや佐々木亮介という男のことを自分は「ロックンロール」と呼びたいと思うほどに。
でも、来年はTHE KEBABSだけじゃなくてa flood of circleでも呼んでくれないとな、と出演が発表された時からずっと思い続けている。ユニゾンは多分来年は普通にメインステージに立っているから。
1.THE KEBABSのテーマ
2.恐竜あらわる
3.チェンソーだ!
4.ロバート・デ・ニーロ
5.ラビュラ
6.THE KEBABSは忙しい
7.ジャキジャキハート
8.THE KEBABSのテーマ
19:25〜 King Gnu [LOTUS STAGE]
中止になった昨年もトリとして出演がアナウンスされていた、King Gnu。そのリベンジとも言えるライブであるし、3年前はまだPARK STAGEに出ていたことを考えるとこのフェスがなかった期間で日本トップクラスのバンドになったということである。
夜になって完全にステージが闇に包まれる中で不穏なSEが響くと、やんちゃな見た目の勢喜遊(ドラム)が力強いビートを刻み始め、そこにメンバーたちが合流してくると、SEのサウンドをそのまま引き継ぐように不穏にアレンジされた「Slumberland」が始まり、常田大希(ボーカル&ギター&キーボード)が拡声器を持って歌い始めるといきなりの特効が炸裂し、ステージは濃いスモークに包まれていく。その不穏な空気とサウンドはまさにディストピアと化している今の日本の情勢をサウンドと視覚の両面で表しているかのようである。
そのステージを覆うスモークがさらに濃くなり、メンバーの姿が見えなくなるくらいになる中で常田がギターに持ち替えたのがわかるサウンドとどっしりとした思い勢喜と新井和輝のベースによるリズムが響くのは「飛行艇」でより太ったように見えなくもない井口理(ボーカル&キーボード)はその美しい声を存分に響かせながら観客の腕を高く掲げて揺らせる。もう完全にこの段階でこのバンドの世界観がロッキンというフェスを飲み込んでしまっているのがわかる。
さらに常田がギターをカッティングしまくるサウンドが心地良くもカッコいい「Sorrows」から、人気アニメのタイアップ曲としてこのバンドの名を一段上のステージにまで引き上げた「BOY」と、前半はアッパーな曲を連発していくのだが、そのサウンドを支えるリズム隊の躍動感は凄まじいものがある。さすがいろんな場所でそのリズムを響かせては腕を磨いている2人である。
そんな前半で早くもバンドの転機となった大ヒット曲の「白日」が演奏され、井口の美しいハイトーンボイスが響き渡るのであるが、この曲がリリースされたばかりの頃に出ていたフェスではこの曲が終わったらステージを移動する人も結構いたりしたのだが、今は全くそんな人がいないというのはこの曲の後にも名曲や代表曲が待っているのをここにいる誰もがわかっているからであるし、何よりこの日のトリとしてのライブだからだろう。
その「白日」からさらに深い深層部分まで潜っていくように常田がピアノを弾いて井口がよりハイトーンかつ痛切な感情を音に乗せるように歌う「The Hole」、さらにはここまでは夜ということもあって薄暗い中での演奏だったのが、タイトルに合わせるように照明がフレーズごとに変わっていく「カメレオン」と聴かせるタイプの曲が続く。持ち時間が長いとはいえ、日本最大規模のフェスのステージでこうした盛り上がるというのとは真逆と言っていいような曲を連続で演奏できるというあたりにこのバンドが時代の勝者になった理由が感じられる。ただただひたすらに楽曲とライブの力でここまで来たバンドということである。
そんな空気を切り裂くように響き渡るのがあまりにも音の強さも手数の多さも凄まじすぎてあんぐりしてしまうくらいの勢喜のドラムソロなのだが、そこから「Vinyl」に繋がるというのはフェスに出始めた頃からの定番の流れであるが、新井のステージ上で踊るような、舞うような演奏も井口のボーカルもドームクラスに立つようになったバンドの力が曲の持つ力をより引き上げているかのようである。
そんな井口は
「あ、喋る喋る(笑)」
と言って喋り出すだけで緊張感すら感じるくらいに張り詰めた空気のライブを和ませてくれるのであるが、前月のNUMBER SHOTでは新井がコロナに感染して新井の演奏する映像を流してのライブだったのが、この日はようやく4人で揃ってライブができることで、
「落ち着きすぎて家にいるみたいになっている(笑)」
と、このステージでこれだけ凄まじいライブをやりながらも口にできる井口はやはり只者ではないなと思う。
その井口のハイトーンボーカルがサビの締めの
「何を信じればいい?」
のフレーズで極まる「Prayer X」から、ここまでの漆黒の闇の中でのライブをカラフルな照明が一変させる「Teenager Forever」では井口がステージ前まで出てきて、ただ上手いだけではなくてロックバンドとしてのエモーションを思いっきり込めた歌唱を響かせる。それは実は銀杏BOYZなどに大きな影響を受けている井口だからこそこのバンドにもたらすことができるロックさであるのだが、その井口の熱量によって観客の興奮のボルテージはさらに向上していく。
それが常田のボーカルにも乗り移るかのような「Flash!!!」ではまたしてもステージが濃いスモークに包まれて、メンバーの姿が見えなくなっていく。その際に井口が何らかのパフォーマンスを準備しているんじゃないかと思ってしまうが、かつてははっちゃけまくっていたこの曲の間奏でもあくまで観客を煽るのみというくらいにパフォーマンスが洗練されてきている。
そんなバンドはまたしても名曲を生み出したばかりであり、その配信リリースされたばかりの新曲「雨燦々」がここで演奏される。照明などの演出がまさに雨を思わせるものになっているのだが、それでもこの日雨が降らなくて良かったと思えるのは視界を遮ることなくこのバンドが演奏している姿を見ることができるからであるし、「傘」という同じように雨をテーマにした曲もあったけれども、今までの曲とは全くタイプの曲を生み出しているというのが本当に恐ろしく感じるし、何よりもどれだけ引き出しがあるんだというくらいのメロディの美しさ。これはもはやタイトルとしても賛美歌のように感じられるような。
そんなライブも終わりの瞬間が迫ってきている。井口は
「今日出演することができて本当に嬉しかったです。ありがとうございました!」
と挨拶をすると、ラストは「逆夢」からの「一途」という映画「呪術廻戦」のテーマソングの2連発。劇場で映画を見た時のエンディングでのこの2曲が続けて流れた時のゾクっとするようなカッコよさをライブという場で何倍にもして感じさせてくれるこのコンボは本当にKing Gnuの数あるタイアップ曲の中でも最も幸福な結果と成果をもたらしたものになったんだなと思うくらいの圧巻さ。全てが代表曲かつ名曲でしかなくて、それを何倍にも増幅させる演奏ができるという、このバンドがこのフェスのトリにまで辿り着いた理由が見れば絶対にわかるような凄まじいライブだった。
それは勢喜のドラムの強さ、新井の踊るようなベースの華麗さ、常田のギターと歌唱のロックさ、井口のエキセントリックでありながらもキャッチーさを備えた曲をさらに大名曲に引き上げる歌唱という異次元レベルのミュージシャンが揃ったこのバンドが、その名の通りに王としてシーンに君臨することを示すようなものだった。
でもきっとこのセトリはフェスだからこそのものでもあるはず。果たしてワンマンではどんな風に驚かせてくれるのか。それを体験してみたくなった。沼っていう表現は安易すぎて使いたくはないが、それでも使わざるを得ないくらいに引きずり込まれそうになっているのがよくわかる。この日、King Gnuはこのフェスのトリを担ってきたバンドたちに名実ともに肩を並べる存在になったのだ。終演後に打ち上がった花火はその祝福であるかのようだった。
1.Slumberland
2.飛行艇
3.Sorrows
4.BOY
5.白日
6.The Hole
7.カメレオン
8.Vinyl
9.Prayer X
10.Teenager Forever
11.Flash!!!
12.雨燦々
13.逆夢
14.一途
20:30〜 四星球 [HILLSIDE STAGE]
そのKing Gnuのライブ後に打ち上がる花火を立ち止まって眺めることなくHILLSIDE STAGEへ駆け出していたのは若干時間が押し気味だっただけにクロージングアクトが始まりそうになっていたから。3年前にはBUMP OF CHICKENの真裏のLAKE STAGEのトリを務めた、ロッキンが誇る最強のクローザー、四星球がこの日のクロージングアクトである。
なのでステージに着いた時にはすでにメンバーが登場していたのだが、北島康雄(ボーカル)の口ぶりから察するにこの日のライブは2020年にタイムスリップしたという設定らしく、U太(ベース)の出で立ちは確かにその年にブレイクした瑛人の「香水」のMVのコンポラリーダンスを踊る人であるのだが、まさやん(ギター)とモリス(ドラム)は見てもよくわからない中で「鋼鉄の段ボーラーまさゆき」からスタートし、観客はエアギターをしたりしながらその場をグルグルと回るという今のライブのルールを守った楽しみ方をしながらタイトル通りにまさやんがフィーチャーされるのかと思いきや、
「前方エリアの奴が遅れて来るな!早く来て待っとけ!」
と前方エリアを当てた人がKing Gnuを見終わってから遅れて来たのを見つけた北島は御立腹で叫び、早くも演奏された「クラーク博士と僕」ではまさやんがギターを何度も空中に投げてキャッチし、北島は段ボール製のハム焼きを持ってまさやんをブン殴りまくる。そんな中でもみんなが早く帰れるようにとこの蘇我スポーツ公演の地図を用意したりと、優しいんだかバイオレンスなんだかよくわからない。
最終的にはまさやんがハム焼きで北島をブン殴って北島がステージに倒れ込むという形で曲が終わるのだが、その北島が倒れている姿を見たまさやんは
「あれ!?あれ、産まれたての仔馬じゃない!?」
と、その産まれたての仔馬が立ち上がるための新曲である「UMA WITH A MISSION」を振り付けを踊りながら歌う。この日は本家であるMAN WITH A MISSIONも出演していただけにもしかしたらコラボもあるかなと思ったりしたのだがそれはなく、京都大作戦などではやたらと時間をかけて立ち上がっていた仔馬こと北島もこの日はすんなり立ち上がるのだが、この曲に時間を使わなかった理由は
「どうしても演奏したい曲があるから」
というものなのだが、その曲はなんとこの日出演キャンセルになったBiSHの「BiSH -星が瞬く夜に-」。この曲を完璧に演奏できるメンバーの鉄壁の演奏技術あってこそできるパフォーマンスであるが、振り付けを観客が完璧に踊っているあたりに今のBiSHがどれだけたくさんの人に愛されているのかということがよくわかる。
実際にこの日はBiSHのTシャツを着た清掃員の方もたくさん会場に来ていて、1番見たかったであろう存在がキャンセルになっても他のバンドのライブで楽しんでいる姿が印象的だった。それはBiSHがいろんなフェスに出演していろんなバンドと対バンしてきたからこそ、他のアーティストのライブを楽しむということが清掃員の方々に浸透しているんじゃないかと思ったし、観客だけではなくて出演者からも愛されてるのもそうした理由だろう。
そんな飛び道具のような正攻法を展開しながら北島は
「このステージのHILLSIDEの意味知ってる人います?丘の中腹っていう意味なんですよ。でも我々中腹で止まるつもりなんてありません!HILLTOPまで辿り着きたいと思ってます!」
と高らかに宣言して「妖怪泣き笑い」では観客を一旦座らせてから一気にジャンプさせる。何なんだろうかこの楽しさと感動は。先月の都内でのワンマン、やっぱり行けば良かったかなと思ってしまうくらいに、凄いライブを見てきた1日が四星球に持っていかれようとしている。それを確かなものにするようにメンバーはこの日使った小道具のパーツを解体してホワイトボードに
「ロッキン大好き」
という文字を作るのであるが、普段ライブが終わった時にやるそのパフォーマンスを今やるのは早くないか?と思っていたら、U太が蹴りを繰り出すかのように激しいアクションを見せ、まさやんは叫ぶようにして歌う「薬草」を、エンタメの力でここにいる人に明日からの生活を生き抜いていくための活力を与えるべく演奏すると、
「ロッキン大好き」
の文字の一部が剥がれ落ちて、それを修復するとなぜか
「ローション大好き」
になり、ステージにはビニールプールと大量のローションが運び込まれてまさやんがローションまみれになるという笑劇のラスト。
「来年から呼ばれなくなったらこれのせいです(笑)」
と北島は言っていたが、フェスのスタッフTシャツを着た人たちも袖で爆笑しながらその様子を見ていた。それくらいに誰しもを笑顔にしてくれるバンドが出禁になるわけがない。むしろこれからも最強のクローザーとしてこのフェスに君臨し続けていくということを示すような、全てを持っていくようなライブだった。北島は
「今日、目をクロージングする時に思い出すライブがこれだからクロージングアクトなんです!」
と言っていたが、もはやクロージングアクトというよりこの日の、いや一週目のロッキンの大トリはこのバンドだったのだ。
メンバーがステージを去っても客席からはアンコールを求める拍手が鳴り続けたのが、北島はそれに応えるために出てきたのかと思いきや、
「メンバーの1人があんなにローションまみれになってアンコールできるわけないやろ!(笑)」
と言ってアンコールはやらずにステージを去っていく。それでもなおもアンコールを求める手拍子が響くとまた北島が出てきて、
「お前らはアホかー!(笑)」
と律儀にツッコミを入れてくれた。いや、それくらいに四星球のライブがもっと見たいくらいに素晴らしいクロージングアクトとしてのライブだったんだよってことはきっと伝わったはずだ。
四星球はまだロッキンに出るようになってからは年数は経っていない。それでもBUMPの裏という誰もやりたくないような位置を立候補したりと、すでにロッキンへの貢献度は計り知れないバンドだ。それくらいにこのバンドは日本で1番巨大なフェスをコミックバンドとして背負おうとしている。それはきっとたくさんの人の思いを背負うことは重荷ではなくて自分たちの力になることをわかっているバンドだからだ。もう来年はメインステージのトリとしてライブを見たいとすら思えるくらいにこの日の全てを掻っ攫っていってしまった。
1.鋼鉄の段ボーラーまさゆき
2.クラーク博士と僕
3.UMA WITH A MISSION
4.BiSH -星が瞬く夜に-
5.妖怪泣き笑い
6.薬草
Panorama Panama Town 「パノパナの日 2022」 @下北沢BASEMENT BAR 8/8 ホーム
ROCK IN JAPAN FES.2022 day1 @蘇我スポーツ公園 8/6